前回の投稿 平和な家庭 ある患者さんとの会話から の続きです。
日本には「水に流す」という言葉があります。
過去のいざこざやわだかまりといったネガティブな出来事をすべて洗い流し、許し合って新たな関係を始めるイメージです。
この感覚は、清らかな水が豊かな日本ならではのものだと筆者は考えています。いつまでも根に持たず、さっぱりとした気持ちで生きていこうとする日本人の姿勢が垣間見えますね。
患者さんとの会話を思い返していると、筆者が日頃から大切にしている神道の祝詞、「一切成就の祓(いっさいじょうじゅのはらえ)」が心に浮かんできました。以下はその祝詞です。
「極めて汚きも溜まり無ければ穢(きたな)きとはあらじ
内外(うちと)の玉垣(たまがき)清く浄し(きよくきよし)と申す。」
この祝詞を、筆者はこう解釈しています。
心に怒りや嫉妬、怠惰な気持ちが湧いても、それに執着せず、川の水のように常に新しい「気」が流れていれば、心は穢れない。
この祝詞を唱えるたびに、筆者は本当に救われる思いがします。なぜなら、いつも心がポジティブでいられるわけではないからです。
「汚れ」とは、恨みや悲しみ、失敗や後悔といった感情を引きずること。「穢れ」は「気枯れ」とも書けるように、出来事や感情を手放せずにいると、気が枯れて元気が失われる状態を指します。
一方、「玉垣」とは、神聖な社殿を囲む石材や木材でできた垣根のこと。筆者はこれを、魂と意識の境目と捉えています。玉垣に汚れがなく、魂と意識がいつもつながっている状態。つまり、心に隔てがない状態をイメージしています。
健康に生きる秘訣は、心が滞ることなく、ころころと転がる小石のように、川の流れのように、常に新しい気が流れ続けること。この祝詞は、そんな生き方を教えてくれていると筆者は感じています。
神道の罪・穢れに関しては、過去ブログで触れております。
鬱と思考



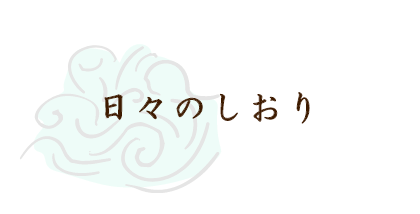
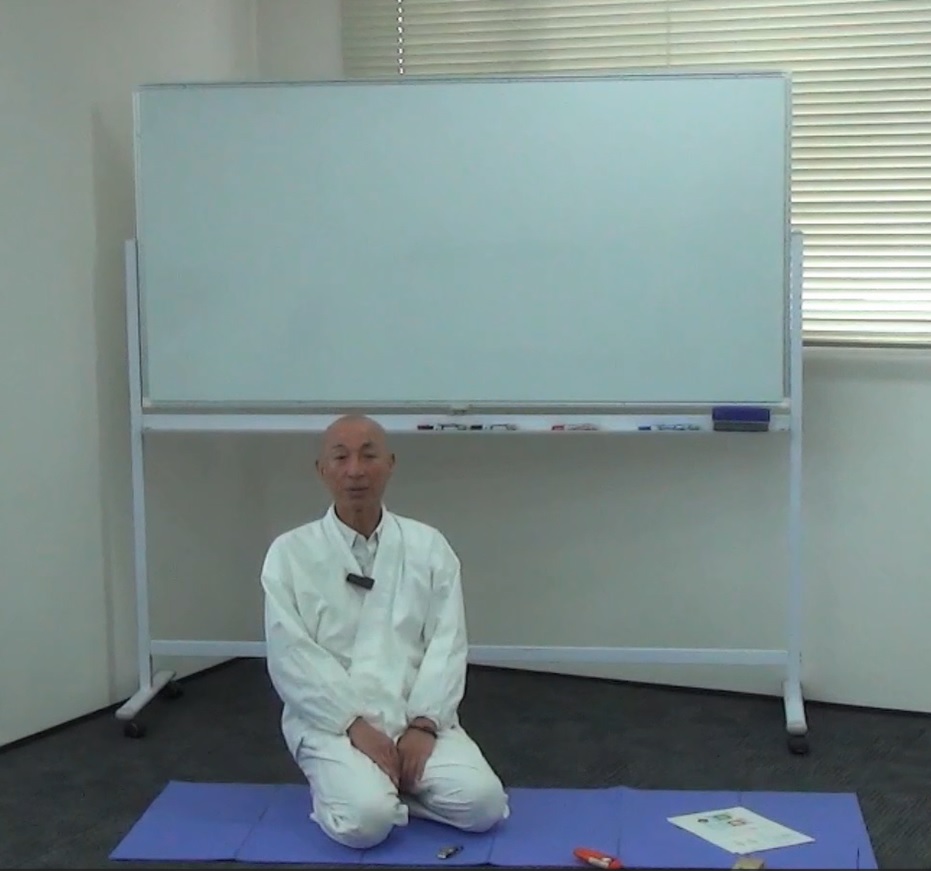



コメントを残す