黄帝が申された。
陰陽というものは、天地大自然の絶対的な法則である。
この世に存在するあらゆるものは、この法則によらないものは無いのである。
春に芽を出し生まれ、秋に死に枯れ生々流転する自然界のあらゆる変化は、目に見えない陰陽二気の消長・転化の法則がその根本にあるからである。
反対にみれば、大自然は陰陽の働きの舞台であり、目に見えないこの働きによって草木は花を咲かせ、実をつけるのである。
このように天地の間で、陰陽二気の神妙なる働きが繰り広げられ、草木1本、傍らの石ころ1個の中にさえ陰陽の法則を見出すことが出来るのである。
人の病の治療に際しては、等しくこの陰陽の法則が働いているのであるから、これを熟知し、陰陽の法則を以て病因・病理を究めなければならないのである。
これは、基本中の基本であり、これを「道に法る」というのである。
であるから、人を深く理解するには、大自然をよく観察するがよい。
陽気の性質は上に昇るのであるから、天は陽気が集積する無形の場であり、陰気は下に降りるのであるから大地は陰気が集積する有形の場である。
陰は静かであり穏やかで動かない性質であり、陽は騒がしく猛々しく活動的である。
陽は生じさせる働きであり、陰は成長を促す働きである。
陽は発散して滅してしまい、陰は収斂して形を堅固にする。
陽は変化を生じさせる気であり、陰は象(かたち)である。
寒の性質は収斂=引き締めるのであるから、対極にある陽気は凝縮されて極まると一転して熱となり、熱の性質は発散・消耗、減であるから、対極にある陰気が長じて極まると一転して寒となるのである。
大好きが極まると大嫌いに転化し、大嫌いが極まると大好きに転化する。
大好きはすなわち大嫌いであり、大嫌いはすなわち大好きなのである。
静かなる鬱積が極まれば爆発し、発散が極まればおとなしい静に転化する。
爆発は静けさであり、静けさは爆発なのである。
手を氷水の入った洗面器に漬けて出すと一転して火照りという熱の症状が現れ、身体が発熱して発汗が過ぎると一転して身体が冷え切って死に至るという現象も同じである。
このように、物事は極点に達すると陰陽の逆転=転化が起きることは、自然の大法則なのである。
陰である寒気は、下に降りて凝り固まるので目に見える濁を生じる。
陽である熱気は、上に昇って拡がって行くものであるから、目に見えない澄んだ清を生じる。
本来昇るべき清気が昇らず、下に留まれば猛々しく動の性質である陽気は、出口を肛門に求めて下痢を起こすのである。
この場合、熱気が下るのであるから便の臭いはきつく、肛門も熱く感じるのである。
また、本来降りるべき濁気が降りず、上に留まればおとなしく静の性格である陰気は、動くことが出来ないので全身の気が停滞し、胸が詰まったかのようになり、さらにお腹も膨れて張って来るのである。
上から降りて来ることが出来ないので、下から上に昇ることも出来ないからである。
これら相反する陰陽の働きが、本来の動きをし、法則に従っておれば順であるので病とならないのである。
ところが本来の動きが出来なくなり、この法則に適っていなければ逆であるので病となるのである。
要するに、自然の法則に従っているか、逆らっているか。こんな単純なことで病気になるかどうかが決まるのである。
天は清陽が昇った無形の場であり、地は濁陰が集まった有形の場である。同じことを繰り返し述べるのは、これが重要であるからだ。
まずは誰にでも分かるように、大自然を大雑把に捉えてみよう。
濁なる地気から生じた清陽の気は、天の気の作用が極まってくる兆しとして雲となり、天の気が極まれば物質化して雨となって濁陰なる大地に下るのである。
雨は天から降りて来るといっても、元々は地気が極まって上昇したものである。
その地気が昇って姿を現す天の雲は、天気の働きによるのである。
このように陰陽・清濁は、天地の間を姿を変えながら生々流転するのである。
これを小自然である人体に応用して説いてみる。
清陽は、上に昇るのであるから人体の天である頭部の耳目口鼻の孔より出入りし、濁陰は下降するのであるから人体の地である尿道と肛門の穴より出て行くのである。
飲食物に含まれる清陽の気は、摂取すると体表に赴き、皮膚より発して全身を陽気で包み、飲食物に含まれる濁陰の気は、栄養物としてすばやく五臓に入るのである。
さらに清陽の気は、手足を充実させて労働を可能にし、濁陰の気は、六腑の消化作用を行う上での物質的基盤になるのである。
万事このように、大自然の気の動きに照らし合わせて人体の気の変化を捉えて行くのである。
象徴としての水は陰であり、火は陽である。火である陽は、人体においては気であり、陰は5つの味の作用を有している飲食物である。
五味を有する飲食物によって肉体は形成され、飲食物によって充実した肉体からは元気が生じる。
元気は物質的に最も尊い人体の物質的基盤である精を作ることが出来、その精は五臓六腑の消化作用を強固にし、飲食物をまったく異なる気血に化する作用を生みだすのである。
精を作り出すには気を消費し、肉体は飲食物を消費することで成り立っているのである。
そして消化という言葉通り、消えて別物になることを化といい動きを変というのである。
この化の作用によって精は生まれるのであり、気によって肉体を育て個体として維持するのである。
これを裏返せば、飲食物の不摂生は肉体を傷害し、肉体が傷害されると気が弱って精も傷害され、精は気を生み出すのであるから、結局は飲食物によって気は傷害されると言うことになる。
要約すれば、過不足なく清潔で正しいものを食べていると、肉体的にも気が充実して精をたくさん作ることが出来、精が充実してくると身体の気血が充実して来る。
反対に、飲食の不摂生をしていると、肉体が弱り気も不足して来るので精を作り出すことが出来なくなってくるということである。
気は精をその根にしているので、結局のところ気は、飲食の不摂生によって傷害されるのである。
飲食物は有形であるから陰であり、水である。水は陽気を内包している。
飲食物は有形であるために下降して、尿道と肛門から排泄される。
飲食物の陽気は、無形であるために頭部にある鼻・口・耳・目などの穴から排泄されるのである。このように、飲食物には、陰陽の二気が内包されているのである。
その内の陰気に焦点を当てると、味の厚い濃厚な飲食物は、陰中の陰であり、味の薄い飲食物は陰中の陽である。
次に陽気についてみると、気の厚い酒や熱いものなどは陽中の陽であり、気の薄い薬味や適度な温かさのものは陽中の陰である。
さて、味の厚い濃厚な飲食物は陰中の陰であるがゆえに、下降・停滞の性質が強いので泄瀉を起こし、薄いものは陰中の陽であるがゆえに、上昇・活発の性質が強まるので全身の気血がよく回って通じるのである。
そして陽気の薄い飲食物は、発汗する程度であるが、陽気の厚い飲食物は、当然のことながら発熱するのである。
体温が異常に高い壮火であると気は衰え、正常である少火は、気を壮んにする。
壮火は気を消耗させ、気は少火に養われる。
壮火というのは陽気過剰であるから気を発散させてしまい、少火は気を益々充実させるのである。
さて、酸・苦・甘・辛・鹹の五味の働きを気味というのであるが、それらを陰陽に分類すると、辛は舌を刺してピリピリとして熱を生じ、甘は柔らかく緩めて気を停滞させるので熱を生じ、共に熱は発散の作用があるので陽である。
酸はツーンとした刺激で引き締める作用があり、苦は苦痛を生じて我慢するので固める作用があり、共に気を内に閉じ込める作用があるので陰である。内に閉じ込められた気は口・肛門から出て行くので涌泄、つまり吐下の作用があるのである。
正常無病の人は、陰陽二気が上手くバランスを保っているが、陰陽二気が大きくどちらかに偏在する時には病気となるのである。
陰が盛んであると陽が病み、陽が盛んであると陰が病む。
その姿は、陽は火の性質なので陰に勝って盛んになり過ぎると熱を生じ、陰は水の性質なので陽に勝って盛んになり過ぎると寒を生じるのである。
寒によって陽気が内に閉じ込められ、極点に達すると熱するようになる。
熱によって陽気が外に発散し、極点に達すると寒するようになる。これを陰陽の転化法則という。
寒は収斂の働きがあるので肉体を傷害し、熱は発散の働きがあるので気を傷害する。
寒は肉体を傷害し、熱は気を傷害する。
気が傷害されると通じさせる力がないので痛みを生じ、肉体が寒に傷害されると寒によって閉じ込められた内部の熱がせめぎ合って停滞するので腫れを生じる。
したがって、まず初めに痛みがあった後に腫れて来るものは、気の傷害が肉体に及んだものであり、反対にまず腫れを生じてから後に痛んでくるのは、肉体の傷害が気に及んだものである。
風気が過ぎると突然倒れたり震え・痙攣が生じ、熱気が過剰であると出口が渋滞して赤く腫れ、燥気が過ぎると血不足のように乾き、寒が過剰であると体液が動かなくなるので浮腫が生じ、陰邪である湿気が過ぎると胃腸を傷害されて下痢を起こすのである。
天には春夏秋冬の四季と木火土金水の五行がある。
春は生じ、夏は長じ、秋は収め、冬は蔵する。
この天の四季の変化に伴って木火土金水の五気が生じ風寒暑湿燥の五気が生じる。
春は木で風、夏は火で暑、長夏(中国では湿気の多い季節)は土で湿、秋は金で燥、冬は水で寒といった具合である。
人においては、この自然界の天の働きによって生じた五気が五臓の働きに相当する。この五臓の気によって喜怒悲憂恐の感情が生じるのである。
人体の天の気である喜怒が過ぎると気が障害され、自然界の寒暑が過ぎると肉体を傷害するのである。
精神情緒の面から見ると、激しい怒気は、熱化して上昇するので血(けつ)を激しく消耗するので、陰血を傷害することとなる。
喜びという感情は、緩める作用があるので、激しく喜びが過ぎると気が散ってしまい陽気を傷害することになる。
気が滞り下降すべきものが上に一気に上に上ってくると、脈がいっぱいになって詰まって動かなくなり、神気は肉体を去ることになるので意識障害か死亡に至るのである。
喜怒に節度が無くほしいままにし、自然界の寒暑が度を過ぎていたり処し方を誤ると、生命そのものが危うくなるのである。
一方、肉体面に目を向けると、極まると転化する陰陽の法則のとおり、陰を重ねると必ず陽に転化し、陽を重ねると必ず陰となる。
従って、冬に寒に傷害されると春に温病となり、春に風に傷害されると夏に消化不良の下痢を起こし、夏に暑に傷害されると秋に寒熱が往来する瘧(おこり)となり、秋に湿に傷害されると、冬に咳嗽を生じるようになるのである。
黄帝が申される。
余が聞くところでは、上古の聖人が人の形(臧)を論じて整理し、蔵府を分類して列挙し、端に経脈を関連づけた。これは六合(陰=臓腑)に相通じ、それぞれの蔵府が各経脈に従っている。
さらにそれぞれの経には、体内の気が体表に発する穴があり、それぞれに名称がある。
大きな肉の合わさるところは谷、小さな肉の合わさるところは谿であるが、それらはすべて骨に連なっているが、すべて始まるところがあり、身体の部分がどこに従属するかは、それぞれ条理がある。
四時陰陽の変化には、すべて法則があるのと同様に、自分と外界である自然界の対応変化は、全て身体の表裏の気の変化に見て取れると言う。これらは、信じて良いのだろうか。
岐伯が問いに対して以下のように答えた。
東方は日が昇り、陽気が上昇して空気が動き始めるので東方は風を生じるのである。
風が動き始めることによって、他の気も動き始めるので木は育ち、木は酸味の果実を生じる。
酸は肝の陰気を補いそれによって筋を養う。日の出からやがて日中がやってくるように、筋が十分に補養されていると心を生じるのである。そして肝は神気が現れる目を主る。
これらのことは、天にあっては霊妙な萬物発生の作用である玄であり、人においてはこれが法則となる道なのである。
大地は、何もないように映るところに万物を生じさせる働きがあり、これを「化」と言う。
この化の作用によって酸・苦・甘・辛・鹹の五味が生じ、自然界の法則を認識することができる人間には、智慧が生じ、玄である天の霊妙な働きは、陰陽の法則で測り知ることのできない「神」を生じるのである。
この陰陽の法則で測り知ることのできない変化は、天にあっては風であり、地にあっては木である。
これを人体にあてはめると筋であり、臓においては肝であり、色では蒼の青色であり、音階では角、声の調子は呼、肝の大きな変動は握、九竅では目、肝に入る味は酸、気が向かう方向である志は怒となるのである。
怒は激しく陰血を消耗して肝を傷るが、悲は肝を制御する。激しい変動である風は、肝を傷るが、燥気は風を制御する。過剰な酸味は収斂するので肝気が伸びず障害されるが、発散の辛味は、酸を制御するのである。
南方は、昇った朝日の陽気が最も盛んで熱化するので、熱を生じるのである。熱せられると燃えやすくなるので火を生じ、火は苦味の灰土を生じる。
苦味は心に入って心の陰気を養って血を生じ、血は脾気を生じるのである。そして心は脾気の状態が現れる舌を主る。
これらのことは、天にあっては熱であり、地においては火であり、これを人体にあてはめると常に気血が流れている脈であり、臓においては拍動を自覚できるくらい陽気の強い心であり、色では火熱の赤色であり、音階では徴、声の調子は笑、心の大きな変動は憂、九竅では舌、心に入る味は苦、気が向かう方向である志は喜である。
喜は激しく気がのぼり陽気を発散して心を傷るが、恐れは気を鎮め降し、冷静にさせるので心を制御する。
激しく変動する熱は、気を傷るが、寒気は熱気を制御する。
過剰な苦味は固める作用があるので心気が伸びず障害されるが、潤し柔らかくする鹹味は、苦味を制御するのである。
四方の中央は湿気を生み、日中から黄昏までは、最も湿気の多い時期である。湿は大地である土を育成し、大地から生じた食物はすべて甘味を含んでいるので、甘味は土より生じるのである。
甘味は脾の陰気を養い、脾は肉体を養う。充実した肉体によって肺気が生じ、脾は、肺気の状態が現れる口を主る。
これらのことは、天にあっては湿であり、地においては土であり、これを人体にあてはめると肉付きの状態であり、臓においては脾であり、色では黄色であり、音階では宮、声の調子は歌、心の大きな変動は噦(えつ=しゃっくり)、九竅では口、脾に入る味は甘、気が向かう方向である志は思である。
思は気が一ヶ所に停滞して脾を傷るが、怒は激しく気を動かして上昇させるので脾を制御する。
湿はベトベトして気を停滞させるので肉体を傷害するが、風気の動かし・運ぶ働きによって乾かされるので、風は湿を制御する。
甘味は緩める作用があるので肉体はだらりとして重くなるが、酸味の収斂作用によって引き締めるので、酸は甘を制御するのである。
西方は、一日の内では落陽の時期であり、陽気が衰え空気も乾いて来るので燥を生じるのである。
乾燥すると形が固まるので、燥は金を生じる。辛は、取手のついた大きな鍼であり、辛い味は、鍼で刺すようでつらい感覚を生じる。そこで金は辛を生じるのである。
辛味は気の滞りを発散させ巡らせるので肺を生じ、肺は、発散と固摂の両方の作用を併せ持つ皮毛を生じる。
この皮毛の働きによって水の流れは正常に機能し、腎は正常に機能するので皮毛は水を主る腎を生じるのである。そして肺気の状態は、鼻に現れるので肺は鼻を主るのである。
これらのことは、天にあっては燥であり、地においては金であり、これを人体にあてはめると皮毛は人体の形を維持する袋であり、また直接外気に触れる体表の皮毛であり、臓にあっては、直接外気が出入りする肺である。
色では白、音階では商、声の調子は哭、肺の大きな変動は咳、九竅では鼻、肺に入る味は辛、気が向かう方向である志は憂である。
憂は、気が鬱するので肺を傷るが、気を緩めて発散する喜は、憂を制御する。
過剰な熱気は皮毛を傷るが、寒気は熱気を制御する。過剰な辛味は発散の作用が強いため、皮毛の機能を傷るが、固める作用のある苦味は辛味を制御するのである。
北方は、一日の内では最も陰気が盛んになる時期であり、陽気が衰えて寒気を生じるのである。
寒気は空気中の湿気を水滴に変化させるので、寒は水を生じるのである。塩は水を煮詰めて生成するので水は鹹(かん=塩からい)を生じる。
鹹味は、物の乾きを抑制するので、鹹は潤す作用がある。
鹹味は水臓である腎を潤すので、鹹は腎を生じ、腎は骨の深いところの骨髄を生じるのである。
この最も陰気の盛んな髄から肝が生じ、腎気の状態は耳に現れるので、腎は耳を主るのである。
これらのことは、天にあっては寒であり、地においては水である。
これを人体にあてはめると、人体の空間を形成する骨であり、臓にあっては、人体の最も下部で奥に位置する陰臓たる腎である。
色は黒、音階では羽、声の調子は呻、腎の大きな変動は慄、九竅では耳、腎に入る味は鹹、気が向かう方向である志は恐である。
恐は、気が下降して腰が抜けるようになるので腎を傷るが、気を一ヶ所に留める思は、恐を制御する。
過剰な寒は水を溢れさせて骨を傷るが、水に比べて陽気の強い湿は寒を制御する。
過剰な鹹味は、潤し柔らかくする作用があるので骨を傷るが、気を緩め熱を生じさせ散じて腎水を乾かす作用のある甘味は、鹹味を制御するのである。
天は高くして尊く、万物を覆い、地は卑(ひ)くくして万物を載せる。
天気は下り、地気は上り、天地陰陽の気の変化・交流で万物は生じるのである。
万物にとって天地は生み出す元である父母であり、上下である。
陰陽なるものは、たとえば働いて養う男性と、生み出す女性のように、血は気を生み出し、気は血を導くようなものである。
陰である血と陽である気は、男女の関係と同様なのである。
人が南面して立てば、左は東で陽気が生じ始め、右は西で陽気は没する。
このように、陰陽の消長は左右という場に、その変化が現れるのであるから、左右は陰陽の道路というのである。
天の気である風・寒・暑・湿・燥は、無形であって直接目で見ることはできない。
しかしながら天の気を受けた大地の気は、木・火・土・金・水に象徴され、有形であってしかも具体的に確認できる。
これらの内、人体にあって水火は気・血であり、神気・精であり、最も陰陽の変化の兆しを察知することができる、目付どころである。
天地陰陽の二気によってすべての現象が始まる。これを大前提とする。
人体においては、先天の水火である神気・精がこれに相当する。
陰気は、身体内部にあって陽気を養い、さらに陽気が散逸してしまわないようにしっかりと守っているのである。
体外に現れた陽気は、体内が外邪に侵されないように働くのであるから、陽は陰の使いなのである。
陰気は求心性であり、陽気は遠心性である。
陽気の活動は、陰気が手綱を握っているのである。
男女もまた然りである。
黄帝が申されるには「陰陽に法るとは、どのようなことなのか」と。
岐伯が、以下のようにお答えした。
陽が盛んになり、身体が熱せられると、本来であれば毛穴が開いて熱を体外に逃がすのであるが、もし毛穴が閉じてしまった場合、熱が体内に籠ってしまうのである。
そうなってしまうと、走ってもいないのに粗い喘ぎが現れて、うつ伏せになったり仰向けになったりして苦しむことになる。
毛穴が閉じているので、汗が出なくてさらに鬱して発熱すれば、歯も乾いてしまって悶え苦しむ。
陽気である熱が出口を無くしているので、腹が満ちて死に至るのである。
寒気の盛んな冬であれば、なんとか持ち堪えるかもしれないが、陽気の盛んな夏であれば堪えることはできないものである。
今度は反対に、陰が盛んになり、身体が寒くなると、本来であれば毛穴を閉じて陽気を漏さないのですが、もし毛穴が開いたままになると陽気が出てしまい、身体は常に水が清んでいるかのように静かになってしまう。
そうなってしまうと、しばしば戦慄して寒気を覚え、寒が甚だしくなると手足に陽気が巡らず、手足が冷え上がってくる厥という状態になる。
厥ともなれば、陰気である寒が気血を停滞させ、腹に満ちて死に至るのである。
陽気の盛んな夏には持ち堪えることができるかもしれないが、陰気の盛んな冬であれば堪えることができないものである。
これら病の形態は、陰陽のいずれかに大きく傾いた時に、この法則にかなっていない場合に起きる基本形である。
黄帝が申されるには、「それでは、これら陰陽の二気を調和させるには、どのようなことが肝要であるのか」と。
岐伯が申し上げた。
男女の盛衰は、天寿を全うする(4)素問-上古天真論で、すでに述べております。
女子は七の倍数、男子は八の倍数でそれぞれ盛衰すると以前申し上げましたが、ここで改めて整理いたします。
七損とは、女子=五七、六七、七七の三段階。男子=五八、六八、七八、八八の四段階。合わせて七段階で衰える。
八益とは、女子=一七、二七、三七、四七の四段階。男子=一八、二八、三八、四八の四段階。合わせて八段階で充実するということであります。
この七損八益の各段階における各臓腑の生理機能の盛衰を、熟知して養生することが肝要であります。
このことを知らず、天道に背くような身勝手な生活を送っていれば、七損の下り坂を一気に早めて、老い衰えるのであります。
四十歳では、陰気である精は自然と半分程度になるので、起居も衰えてくるものであります。
五十歳になれば、さらに身体が重く感じ、耳目もはっきりとしなくなってくる。
六十歳ともなれば、性器は萎え、臓腑の気も大いに衰えてしまうので、耳目鼻口前後の二陰全ての機能が、ままならなくなるのであります。
そして、下半身の陽気は昇らず、上半身の陰気は下りない、いわゆる上実下虚の状態となり、涙もろくなるのである。
ゆえに、七損八益の理を踏まえて養生すれば強盛を保つが、これを知らずにいい加減に過ごしていると、早く衰えるのである。
等しくこの世に生を受けた者同士であっても、理に適った養生によって、強ともなり、早老ともなるだけのことである。
智者は、自然の変化を察して自ずと適い、愚者は目先のものを察して天道と異にするのである
従って愚者の精血は不足し、智者は有余しているので、耳目は聡明で身体も軽く強壮であり、老いてなお壮んで、益々天道に適うので強壮となるのである。
天地陰陽の法則と一体となっていた、聖人と称される人物は、事を意識しなくして行動しても、自ずと理に適った無為の境地にあるのである。
そのような聖人は、物事にこだわらず、何があってもさらりと受け流し、心穏やかで平和な状態を楽しむのである。
そして自ら欲するまま行動するが、自然の法則に適った、こだわりの無い自由な心を守ることを、心地好しとしていたのである。
従って寿命は窮まることなく、天地の終わるまで続くのである。
これが聖人の身を治める養生法である。
天の気は、北西に不足するので、西北方は陰である。
そして人の右の耳目は、左ほどはっきりとしていない。
地の気は、東南に満ちることが無いので、東南方は陽である。
そして人の左の手足は、右のように強くないのが常人であると言う。
帝は、「何を根拠にこのようなことを述べているのであろうか」と申された。
そこで岐伯は、以下のようにお答えした。
東方は陽気が昇り始めるので、人体の精は陽気と相まって上に集まるのである。
上に集まるところは、明らかとしてはっきりとし、その下は虚ろとなるのが道理であります。
したがって、天の気である神気が出入りする感覚器=左の耳目は聡明になるが、地気の濁氣を受けて機能する運動器=下方の左の手足はあまり利かないものである。
西方は陰気が盛んになり始めるので、人体の精は陰気と相まって下に集まるのである。
下に集まるところが盛んとなるので、上は虚ろとなるのが道理であります。
したがって、右の耳目は聡明でなく、右の手足は都合よく利いてくれるのである。
このようにして、天の気の偏在が、そのまま一般的な人間の利き目・耳、利き手・足を生じさせるのである。
したがって、邪気が左右に等しく襲ったとしても、その邪が上にあれば右の耳目が甚だしく症状が現れ、邪が下にあると左の手足が甚だしく症状が現れるのである。
これらは、天地の空間的場において、陰陽が消長(偏在)するために、完全に等しいということが存在しえないからである。
そして邪は、その精気が虚ろなところに居つくのである。
天には無形の精があり、地には形として存在する。
天には四季八節があり、天気が下る地には五行がある。
この天地の交流によって万物は生まれるのであるから、天地は父母のようなものである。
無形の清陽は天に昇り、有形の濁陰は地に帰るのであった。
そして天地の動静は、直接目には見えないが、明らかにそれと分かる神が、しめくくり、主っているのである。
この神によって、天地の間に四季の変化が生まれ、生長収蔵の変化の循環が、延々と繰り広げられるのである。
巷では、ただ賢人と称される人のみが、上は天にならって頭を養い、下は大地の在りようにならって足を養い、上下の中は、人間としてなすべきことに従って五臓を養うのである。
天の気は肺に通じており、地の気は食道に通じている。
風の気は肝に通じ、雷の気は心に通じ、穀の気は脾に通じ、雨の気は腎に通じ、それぞれ天地の気と臓の気は相応じているのである。
三陰三陽の六経は川であり、腸胃は海である。
水の清なるものは、頭部の上竅に通じ、水の濁なるものは下部の下竅に通じている。
天地を以て、これを陰陽と為すのであった。
であるから、人体の体液が熱せられると、上に昇って汗として発せられる。これを天地になぞらえれば雨である。
人体の陽気は、全身を素早く巡っているので、天地になぞらえると疾風である。
暴気は雷の現象であり、逆気は立ち上る陽気の現象にかたどるのである。
このように、人体の生理は自然界の陰陽法則と相応じているのである。
したがって、天の気の移り変わりの変化法則に法り、天に従って変化する地の条理を用いて治療すべきである。
もし、これらに背くような治療を施せば、当然治らないどころか災害に至らせることになるのである。
人を害する邪を伴った風が至る様は、矢のように早く、しかも激しいもので、まるで風雨の如きである。
したがって、治療に秀でた者は、邪気が皮毛を犯した段階で治めてしまうのである。
邪気は、皮毛→皮膚→筋脈→六腑→五臓と侵入するのであるから、治療者は、邪気がどの部位に居るのか見定めてから治療するのが肝要である。
ところが五臓に邪気の侵入を許してしまってから治療すれば、もう手遅れとなってしまい、半分程度しか助からないのである。
このように、外邪としての天の邪気を感受すれば、最終的には人の五臓を害し、死に至ることが多いのである。
飲食物の寒熱が、その度を越えて大きく偏っていれば、水穀の海であり、直接飲食物が納まる六腑が障害され嘔吐・下痢などを生じる。これは内因である。
また外邪としての地の陰邪である湿気を感受すれば、陽気が阻まれて皮膚病が生じたり、筋脈が思うように動かなくなる病を生じるのである。
『陰は内にあり、陽の守なり。陽は外にあり、陰の使なり。』
体外に現れた陽気は、体内が外邪に侵されないように働くのであるから、陽は陰の使いなのであり、陰気は求心性であり、陽気は遠心性ということであった。
さらに『左右は陰陽の道路』
陰陽の消長は左右という場に、その変化が現れるということであった。
鍼を用いるのに巧みな者は、これらのことを熟知して自然の法則=道に法った治療を行うのである。
つまり、内外・表裏の陰陽関係の虚実をよく見極め、陰に邪があれば正邪抗争の場を陽に移動させるのが得策である。
反対に、正邪抗争の場が陽にあれば、陽の守りである陰を鼓舞するのが道理に適っているのである。
さらにこれを、上下と読み替えることも可能である。
左右も同様である。
相対的に、左に気が偏在しているのなら右に鍼をし、右に気が偏在しているのなら左に鍼をして、陰陽の平衡を一旦整え、自ずと陰陽が消長するよう導けば、治癒するのである。
そして治療者は、自分を基準として患者の状態を把握するのであるから、自分を正常な、良い状態にしておかなくてはならないのである。
このような熟達した治療者は、陽である表の状態を診て、陰である裏の状態を察知し、陰陽の過と不及。
つまり陰陽の有余・不足、平衡・虚実を見定めるのである。
そして、かすかな雲行きから天気の大きな崩れを予測するように、微かな兆候から有余・不足を的確に把握し得た後に治療するのであるから、鍼を用いて誤るということがないのである。
すぐれた医師は、患者の現す顔の気色や肌の色から、体内で何が起きているのかを察し、脈が表現している気の状態をじっくりと味わうように診る。
そうしてから、先ず患者の病が、陰陽のいずれに属するのかを判断するのである。
そこからさらに、上下清濁を審らかにし、全体の状態を把握しながら、病んでいる部分を理解する。
喘ぎや息づかいを意識的に視、患者の発する声の強弱や清濁に耳を傾け、苦しむところがどこにあるのかを知るのである。
觀權衡規矩(けんこうきく=四季の脈状、脈要精微論に記載)、つまり四季の脈を基準にして、今現在患者の脈が四季の脈と反していることの意味を読み取り、病の根本がどこにあるのかを知る。
つまり夏は体表の浅いところを脈拍つべきであるのに沈んでいたり、冬は深いところを脈拍つべきであるのに浅いところに浮いていたり、といったことである。
脈の寸口・尺中を按じて、搏動部位の深浅、脈の去来が滑らかであるか渋っているかを観て、病の生じたところを知って、治療を施せば、過ちはない。
つまり、まずは目で視、耳で聞き、指先の感覚を以て、陰陽の偏在をはっきりとさせることである。
このように診察・診断を行えば、患者の精気を失うような失敗は無いのである。
病が起こったばかりの初期においては、刺法を施せば直ちに癒えるものである。
病勢が盛んになってしまってからでは、刺法を施しつつ次第に病勢が衰えるのを観察しながら治癒に導くのである。
病邪の侵入が浅く程度が軽いようであれば、発揚して散じ、邪気の重さと正気の兼ね合いを計りながら病邪を減じ、病勢が衰えてくると、鍼の効果がはっきりと彰(あきら)かとなるのである。
身体の気が虚しているものには、温めて気虚を補い、精血が不足しているものには、飲食物の五味でこれを補うようにする。
病が上焦にあるものは、さらに上方へ発揚させ、下焦にあるものは、さらに下に引いて邪が尽きるようにする。中焦に邪気が充満するものは、直接臓腑に瀉法を加える。
その邪気が比較的深い場合は、薬湯に体を漬けて発汗させ、邪気が比較的浅い皮にあれば、発汗法を用いて発散させるのである。
その病状の進展が速く、病勢が激しいものであっても、症状に動揺することなく落ち着いてじっくりと対峙して考え、間違いのないように収めるのである。
正気はまだ傷害されておらず、邪気が盛んであるものは、散じることでこれを瀉すのである。
その際には、陰陽をはっきりと審らかにし、その上で剛柔・虚実を別け、陽病は陰を治療し、陰病は陽を治療する。
そして血気の状態が安定してくれば、正気はそれぞれ本来の臓腑・経絡をしっかりと守るようになる。
血が充満して苦しむようであれば、あふれる寸前の川の堤を切るように瀉血し、気が虚していれば、気が漏れたり散じてしまわないように、補法を加えて引き締めるのである。


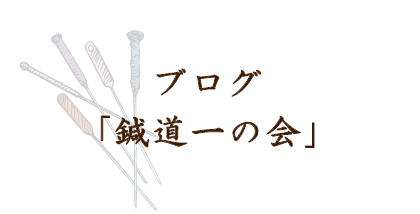



コメントを残す