五行論と季節は関連付けられていますが、日本ではその順序が合わないのが、夏の後にやってくる「長夏」です。
中国大陸では、夏の後に「長夏」と言って梅雨のような季節が存在しますが、日本では春と夏の間に湿気の多い梅雨があります。
これは日本と中国の気候の違いによるものですので、五行論をそのまま鵜呑みにして機械的に当てはめると誤ることになります。
しかし、この梅雨特有の気候が人体に及ぼす影響を理解しておくと、治療や養生に役立ちます。
一般に日本家屋は、冬の寒さよりも梅雨から夏にかけての高温多湿を意識した、風通しの良い作りになっています。
人体においても、風通しの良い衣服が良いでしょう。また、心においても、いつまでもわだかまっているよりも、さらりと受け流して爽やかな気持ちでいるのが良いと思いますが、なかなかそこは修行ですよね。
日本には「水に流す」という言葉があるくらいですから、わだかまりを持たない文化は素晴らしいと思います。
このあたりのことは、ブログ「日々のしおり」<水に流す文化>で触れていますので、興味を持たれた方はリンク貼ってますのでご覧ください。
この時期五臓の中では、脾が最もその影響を受けますので、津液の新陳代謝を意識するのが良いでしょう。
日本の梅雨は高温で多湿なため、たくさん汗をかいても蒸発せず、肌表面がベトベトして汗孔を塞いでしまいます。そのため、津液の出口は主に小便と呼気になります。
脾の臓は四肢を主るので、適度に手足を動かす運動がとても重要です。
ところが、雨天が続くと散歩やジョギングが難しいため、筆者は室内で体操やヨガ、呼吸瞑想などを行います。意識的な呼吸法は、推動作用の強い宗気を高めるため、梅雨に限らず日常的に行うのが良いですね。
そのあたりのことは、「自分とつながる呼吸瞑想会」でお伝えしていますので、興味のある方はぜひ一度ご参加いただければと思います。
そして大切なのは飲食物です。
湿気が多くムワッとした天候だと、どうしてもさっぱりとした冷たいものが美味しく感じます。しかし、アイスやゼリー、ビールなどの冷たいものや生ものは陽気を傷つけ、新陳代謝が落ちて津液の巡りが悪くなり、脾胃の不調を招くので注意が必要です。
また、甘いものやヨーグルト、油の多い肉なども内湿を高めるため、控えるのが賢明です。
さらに体内の「湿」を停滞させないよう、発汗や利尿によって体外に排出する「利水」の作用がある食材を摂るのも良いでしょう。
消化や発汗を助ける香味野菜やセロリ、ネギ、ショウガ、小豆やハト麦の煮汁などを摂るとさらに良いですね。
ちなみに、小豆やハト麦は漢方でも用いられており、清熱と利水の効果があります。
15グラムを水600ccで煮て半量にし、2~3回に分けて飲むと小便がよく出ます。もちろん、煎じあがった小豆やハト麦を食べても構いません。
筆者はこの梅雨の時期に、好んでスーパー銭湯へ行き、サウナでさっと汗をかくといった工夫もしています。
このようなこと、治療者自らが実践して、体感したことを患者さんに養生法としてお伝えするのも立派な治療になりますし、自らの徳を積むことにもつながります。
ご縁のある方に、元気になって頂きましょう。そして、自らも。



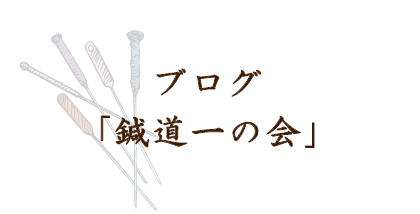


コメントを残す