膨張・発散の夏から穏やかに収縮し、冬へと向かうのが秋の季節です。
『素問』では、この時期を「容平(ようへい)」と象徴的に表現しています。「容」とは入れ物を意味し、万物の形が定まる時期を指します。たとえば、形が定まる植物の実りがイメージされますね。
秋の気は、収束・収斂・収縮といったイメージで理解して頂ければと思います。
人体の生理においても、気温の低下に伴い毛穴が徐々に閉じる傾向にあります。これにより、気の中心が上半身から下半身へと次第に下降します。同時に、夏の間外に張り出していた陽気も徐々に内に向かいます。
毛穴が閉じて汗をかかなくなるということは、汗=津液+熱であるため、代謝がうまくいかないと津液と内熱が過剰となり、さまざまな症状が現れることがあります。
現代では、秋の花粉症がその代表例として挙げられます。自然界と人体の気の相関を理解すれば、病理は比較的容易に解明できるでしょう。
現代人は肉体労働から頭脳労働へと移行し、自動車や交通機関の発達により身体を使って歩く機会が減りました。さらに、冷房の普及により汗をかくことが少なくなり、体内に熱と津液が蓄積しやすくなっています。
加えて、冷たい飲食物の摂取は内側から代謝を低下させます。イメージとしては、体内に水と熱が過剰に溜まった状態です。そこに秋の収斂の気が作用すると、まるで雑巾を絞るように水が鼻水となって溢れ出すのが花粉症の症状です。
本来なら、津液を小便として排出できれば問題は起こりにくいのですが、ここにメンタルが大きく関わってきます。
原文には、「志を安寧にし、以って秋刑を緩める」とあります。「刑」とは、首と手を木枠で固定し、刀で切り落とすという恐ろしい処罰を意味します。
秋は収斂の気が自然界に満ち、植物をはじめ動きが抑えられ枯れて参ります。
この収斂の気を緩めるためには、気ぜわしく動き回ったり、心がせかせかと緊張・興奮状態にならないように養生するのが大切です。
緊張・興奮すると気は上半身に昇りやすくなります。その結果、津液も気と連動して上昇し、鼻から出口を求めて鼻水の症状が現れるのです。
このような病因・病理を理解すると、養生のポイントが見えてきます。夏には適度に汗をかいて体を涼しく保ち、冷たい飲食物を控えることが大切です。そして秋には、軽く汗をかく程度の運動や体操で気を巡らせ、多忙な日常の中でほっと落ち着ける時間を意識的に増やすことが養生の鍵となります。
花粉症は「国民病」とも呼ばれ、さまざまな原因が指摘されています。しかし、東洋医学の視点からは、現代社会の労働形態、生活習慣、飲食習慣が複雑に絡み合い、気滞や津液・内熱の代謝異常が引き起こしていると考えられます。
さらに、アトピーや喘息や精神疾患など、季節によって症状の軽重がある疾患においても、自然界の気の変化を意識しながら病因・病理を追うと、新たな気づきが得られるでしょう。



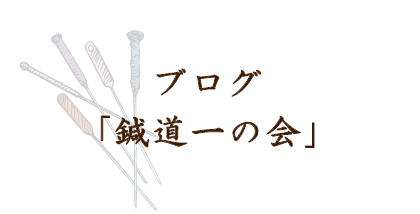


コメントを残す