【四〇条】
傷寒、表不解、心下有水氣、乾嘔、發熱而欬、或渴、或利、或噎、或小便不利、少腹滿、或喘者、小青龍湯主之。方十。
傷寒、表解(げ)せず、心下に水氣有り、乾嘔(かんおう)し、發熱して欬(がい)し、或いは渴は(かっ)し、或いは利(り)し、或いは噎(いっ)し、或いは小便不利し、少腹滿し、或いは喘(ぜん)する者は、小青龍湯之を主る。方十。
方剤構成をざっくり見ると、確かに水を動かす辛温剤である乾姜・細辛が配されていますが、同じく燥湿化痰の辛温剤の半夏もまた配剤されています。
半夏の量が最も多く配されていることから、おそらく心下が水と痰で塞がり、上焦と中焦の気が通じにくくなっているのだと考えられます。
さらにまた、方剤中に胸間の停水を治する杏仁が配されていません。
このことからも、中焦の津液が心下で痰に阻まれ、発汗に十分必要な水が胸間に達していないと考えられます。
ですからたとえ傷寒証であっても、心下に痰が存在すれば麻黄湯類を用いても十分な発汗が得られず、したがって表証も解けないということになります。
「心下に水気あり」とは、腹診で確認できる場合があるということで、実際の臨床では振水音が確認できない場合もあります。
振水音が確認できない場合は、水と痰が結実していると推測することが出来ます。
生理学的にも、上焦は中焦の気を受けて宣散・粛降します。
経絡流注的見地からも、手太陰肺経は中焦に起こり、膈を貫いて肺の臓に流注しています。
これらのことからも、小青龍湯証は心下に水と痰が結んで津液が上焦に昇りにくくなっている状態もあると、考えることができます。
前回、<金匱要略・痰飲咳嗽病>で解説しましたように、小青龍湯が溢飮と支飲の両方に用いられる理由が見えてくると思います。
大青龍湯は、表の水が中心の病態。
小青龍湯は、裏の水と痰が中心の病態で、どちらも表寒で実証であると、まとめることが出来ます。
これらを踏まえて、次回各症状をみていきます。
〔小青龍湯方〕
麻黄(去節) 芍藥 細辛 乾薑 甘草(炙) 桂枝(各三兩去皮) 五味子(半升) 半夏(半升洗)
右八味、以水一斗、先煮麻黄減二升、去上沫、内諸藥。煮取三升、去滓、温服一升。
若渴、去半夏、加栝樓根三兩。
若微利、去麻黄、加蕘花、如一雞子、熬令赤色。
若噎者、去麻黄、加附子一枚、炮。
若小便不利、少腹滿者、去麻黄、加茯苓四兩。
若喘、去麻黄、加杏仁半升、去皮尖。
且蕘花不治利、麻黄主喘、今此語反之、疑非仲景意。
(臣億等謹按小青龍湯大要治水。又按本草蕘花下十二水、若水去利則止也。又按千金形腫者應内麻黄、乃内杏仁者、以麻黄發其陽故也、以此證之、豈非仲景意也。)
麻黄(節を去る) 芍藥 細辛(さいしん) 乾薑 甘草(炙る) 桂枝(各三兩、皮を去る) 五味子(半升) 半夏(半升洗う)
右八味、水一斗を以て、先ず麻黄を煮て二升を減じ、上沫を去り、諸藥を内れ。煮て三升を取り、滓を去り、一升を温服す。
若し渴すれば、半夏を去り、栝樓根(かろこん)三兩を加う。
若し微利(びり)すれば、麻黄を去り、蕘花(じょうか)、一雞子(いちけいし)の如きを熬(い)りて赤色ならしめ加う。
若し噎(いっ)する者は、麻黄を去り、附子一枚を炮(ほう)じて加える。
若し小便不利し、少腹滿する者は、麻黄を去り、茯苓四兩を加える。
若し喘すれば、麻黄を去り、杏仁半升を皮尖を去りて加える。
且つ蕘花(じょうか)は利を治せず、麻黄は喘を主る、今此の語之に反す。疑うは仲景の意にあらず。
(臣億等謹按小青龍湯大要治水。又按本草蕘花下十二水、若水去利則止也。又按千金形腫者應内麻黄、乃内杏仁者、以麻黄發其陽故也、以此證之、豈非仲景意也。)


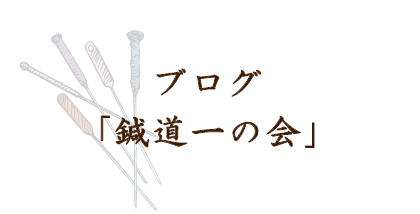



コメントを残す