いよいよ最後の四逆湯証のところに参りました。
「若し重ねて汗を發し、復た燒鍼(しょうしん)を加うる者は、四逆湯之を主る」
これは最初の「傷寒の脉浮、自ずと汗出で、小便數(さく)、心煩、微惡寒し、脚(きゃく)攣急(れんきゅう)」に桂枝湯で一度発汗させ、甘草乾姜湯証にまで病位を落としてしまった壊病でした。
すると「厥(けつ)し、咽中乾き、煩躁吐逆」という症候が現れています。
厥は手足の冷えですから、陽虚です。
咽中が乾くのは、清陽が虚してしまって津液を蒸騰できないからです。
煩躁は、陽虚となり残りの陽気が内に結んで動かなくなるので、もだえ苦しむようになります。
煩躁は、陽明腑実証でも起きますが、この場合は発熱しますので鑑別を誤ることはないと思います。
そして吐逆は、胃の気が虚して不和が起きているからと理解されます。
この陽虚証に対して、さらに桂枝湯を服用させるか、さらに焼鍼を用いるなどしてさらに発汗させると、亡陽に至ってしまうことを言っているのだと思います。
そうなるといよいよ甘草乾姜湯に生の附子を加えた、四逆湯の適応となってしまいます。
四逆湯症は、一般的には重篤な陽虚証とされていますが、配剤を吟味すると乾姜・附子はともに気味辛温です。
乾姜・附子は回陽薬ですが、温めて水を散らす・排泄させる方剤と理解するのが良いでしょう。
ですから四逆湯を服用すると、手足が温まるだけでなく小便利となるはずです。
つまり、陰気である水を排泄することで、相対的に身体全体を陽に持って行き、正気の回復を計るのだと理解されます。
ここで、現在の温補という考え方そのものを根底から考え直す必要が出てくる訳です。
言葉を換えれば、補瀉論にもつながってくる訳です。
鍼を用いるとすれば、三焦のくくりである臍=神闕などの外、下焦に気が集まるような経穴の中から選穴し、脈や気色を診ながらの温補で良いと思います。
この辺りは、病位と病理をつかんでさえいれば、それぞれの流派や患者の状態によって、自由な選穴・治療が可能だと思います。
【二九条】
傷寒脉浮、自汗出、小便數、心煩、微惡寒、脚攣急、反與桂枝、欲攻其表、此誤也。得之便厥、咽中乾、煩躁吐逆者、作甘草乾薑湯與之、以復其陽。若厥愈足温者、更作芍藥甘草湯與之、其脚即伸。若胃氣不和讝語者、少與調胃承氣湯。若重發汗、復加燒鍼者、四逆湯主之。方十六。
傷寒の脉浮、自ずと汗出で、小便數(さく)、心煩、微惡寒し、脚(きゃく)攣急(れんきゅう)するに、反って桂枝を與(あた)え、其の表を攻めんと欲するは、此れ誤りなり。之を得れば便(すなわ)ち厥(けつ)し、咽中乾き、煩躁吐逆する者は、甘草乾薑湯(かんぞうかんきょうとう)を作り之に與え、以て其の陽を復す。若し厥愈え足温かなる者は、更に芍藥甘草湯を作り之を與うれば、其の脚即ち伸びる。若し胃氣和せず讝語(せんご)する者は、少しく調胃承氣湯(ちょうきじょういとう)を與う。若し重ねて汗を發し、復た燒鍼(しょうしん)を加うる者は、四逆湯之を主る。方十六。
〔甘草乾薑湯方〕
甘草(四兩炙)乾薑(二兩)
右二味、以水三升、煮取一升五合、去滓、分温再服。
甘草(四兩、炙る)乾薑(二兩)
右二味、水三升を以て、煮て一升五合を取る、滓を去り、分かちて温め再服す。
〔芍藥甘草湯方〕
白芍藥甘草(各四兩炙)
右二味、以水三升、煮取一升五合、去滓、分温再服。
白芍藥甘草(各四兩、炙る)
右二味、水三升を以て、煮て一升五合を取る、滓を去り、分かちて温め再服す。
〔調胃承氣湯方〕
大黄(四兩去皮清酒洗)甘草(二兩炙)芒消(半升)
右三味、以水三升、煮取一升、去滓、内芒消、更上火微煮令沸、少少温服之。
大黄(四兩、皮を去り清酒で洗う)甘草(二兩、炙る)芒消(ぼうしょう)(半升)
右三味、水三升を以て、煮て一升を取る、滓を去り、芒消を内(い)れ、更に火に上(の)せて微(すこ)しく煮て沸(わか)せしめ、少少之を温服す。
〔四逆湯方〕
甘草(二兩炙)乾薑(一兩半)附子(一枚生用去皮破八片)
右三味、以水三升、煮取一升二合、去滓、分温再服。強人可大附子一枚、乾薑三兩。
甘草(二兩、炙る)乾薑(一兩半)附子(一枚、生を用い皮を去り八片に破る)
右三味、水三升を以て、煮て一升二合を取り、滓を去り、分かちて温め再服す。強人は大附子一枚、乾薑三兩とすべし。


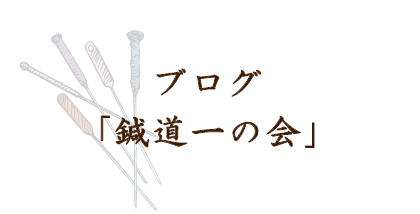



コメントを残す