自然界には、膨張と収縮という相反する二つの気が存在します。
夏になると、万物は気を外へ、そして上へと張り出し、膨張していきます。一方、冬には気を内に収めて収縮します。
この夏と冬の間には、春と秋があり、春は気が外へ向かう穏やかな変化の時期、秋は内へと向かう落ち着きの時期です。人体の気もまた、自然界と同調しながらこうした変化を遂げていきます。
夏に至ると、人体の気は外に張り出し、汗をかきやすくなります。このため、相対的に五臓六腑の気は不足しがちになります。汗は津液(体液)と陽気で構成されているため、汗を多くかくと一時的に気虚の状態に陥りやすくなります。その結果、夏は冬に比べて下痢を起こしやすくなったり、食欲が低下したりすることがあります。いわゆる、夏バテといわれる状態です。
ですから、この時期は虚証になりやすい傾向に陥りがちだということがお判りいただけると、養生や治療に役立てることができます。
逆に、夏に汗をかきにくいとおっしゃる方が、結構いらっしゃいます。アトピーや喘息を患っておられる方に多い傾向にあります。この場合は、実証です。ご本人が自覚しにくいストレス=気滞である場合がほとんどです。
夏に汗をかくことができないと、陽気が内にこもってしまい、それが出口を求めて皮膚症状として現れたり、呼吸がしづらくなったり、喘息などの症状を引き起こすこともあります。
例えば、かつて喘息の持病があった高校生の男子が、夏の暑さの中で過ごした後、帰宅してエアコンの冷風に当たった途端に喘息発作を起こした事例がありました。
また、全身に湿疹が現れた方が、病院で処方された薬を服用してかゆみが治まったと同時に、呼吸がしづらくなったケースもあります。
皮膚は、人体の内部の気と外界をつなぐ重要な役割を果たしているのです。内にこもった湿熱が、出口を皮膚の毛穴に求めて皮膚症状となって現れている時に、薬物で出口を塞いでしまうと、今度は心下を塞いで呼吸がしずらくなるという病理です。
この夏という季節は、なんといっても気が鬱しないよう適度に発散することが大切です。冷房の効いた部屋で四肢を動かさずに座位で事務作業を続け、冷たい飲み物を摂っていると、発散されるべき陽気や津液が体内に滞ってしまいます。特に脾胃への影響が大きいですね。
その影響は秋になって現れ、さまざまな症状を引き起こすことがあります。秋の花粉症などは、その典型的な例と言えるでしょう。
夏には、できるだけ冷たい飲み物を避け、適度な運動や山野への散策を通じて気を外に持っていき、適度に汗をかき、陽気を体内にため込まないように養生を心がけることが肝要です。



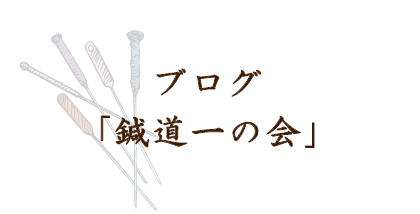


コメントを残す