 |
| これから咲こうとする、花のうれしさ |
前回ブログで『一鍼を下した後の変化をしっかりと捉えると、患者に対する認識はさらに深まり、病の構造も明確になる』と述べたことに関して、例を挙げて説明したい。
例えば、肝鬱気滞と判断される疾患に対して、筋縮穴、もしくは中枢穴の圧痛もしくは熱を確認した上で手を加えると、全体の気の偏在が一気に解消されることがある。
にもかかわらず、脾兪・胃兪の実の変化が見られなかった場合を想定してみる。
一見、肝鬱気滞のように見えていても、実は飲食過多で四肢を主る脾胃に負担がかかっていることが予測される。
では、この場合の肝鬱気滞は、飲食の不摂生・食べ過ぎで身体がだるく、何をするにも億劫になっているところに、しなければならないことがあり、肝鬱気滞を起こしている可能性も存在することになる。
いわゆる疳の虫といわれる小児の場合など、おやつを与え過ぎたことで、理由なくむずがり機嫌が悪いといったケースなどは、よく遭遇する事例であると思う。
大人と言っても、飲食の不摂生でいつも機嫌が悪く、周囲とトラブルを起こしやすく、それが原因となって肝気鬱結を併発し、悪循環に陥っている場合も存在する。
しんどい時に、普段なら聞き流せることが妙に気に引っかかり、不満と怒りが募りイライラするなどといったことは、誰でもが経験していることだとおもう。これと、同じである。
このような場合、肝鬱気滞の原因よりも、飲食を正すことが大切なのであるが、指摘しても自覚すらない患者もいる。
場合によっては、伝え方を選んで進言しても、聞いてはいても入れない者や、中には症状さえ取れればそれでいいのだから何とかしてくれ、と言い放つ患者もいるにはいる。
患者が、いくら否定しようが拒否しようが聞き入れなかろうが、術者が確信のよりどころとするのは患者の身体が表現している事実であり、良くなるための指針は頑として示さなくてはならない。
患者は、自分の身体に起きていることが分からず、その解決を求めてやってきているのである。
術者は患者の訴えにひるむことなく、毅然とした態度を取るべきである。
仮にそれで患者との治療関係を維持できなくなったなら、それは患者自身の不適応である。
通院を重ねても、病の本が治まらないのであれば、病もまた治るはずがない。
これが天上天下、古今東西の道理というものである。
漠然と通院を重ね、病が好転しなければ、患者の失意と不満が医療側に向けられることになり、患者自身の問題解決の焦点が益々ずれることになる。
患者には、拒否され通院が中断したとしても、投じた一石は心に残るものである。
患者の心に蒔かれた種は、いつ・どのようなことがきっかけで芽を出すか分からない、という可能性も残る。
術者たるものは、道士である。
導き、治すという、確固たる信念を持つ必要がある。
そのためにこそ、気を読む術があるのである。
※道士・・・ウィキペディア
(広義)「道術の士」を意味する漢語。「道術」とは『史記』『漢書』においては治世術としての「聖人の道の術」を意味し、儒家も道家もそれぞれに道術の語を用いたが、後の『後漢書』においては、神仙方術、医術、房中術、天文、巫術などさまざまな術を指す「方術」の語とほぼ同じ意味で用いられている。


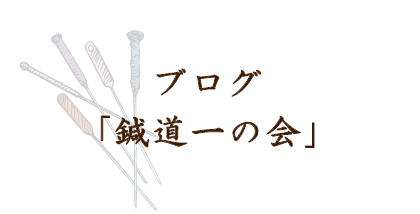
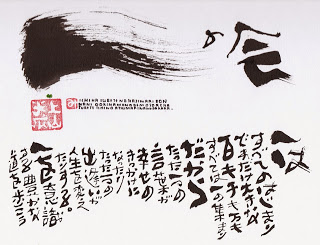
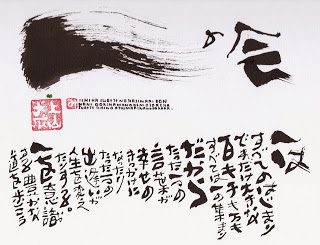


コメントを残す