 |
| 秋の青空と可憐な花 |
左右差は、肝胆の作用によるものとしての認識は、かなり以前から持っていた。
実際、上下だけでなく左右差の大きい身体は、意識・無意識であれ気滞の存在がある。
この場合の気滞とは、七情内鬱と限定しておく。
気滞の初期の腹部所見は、おおむね左は実を起こし、背部は逆に右の実を起こすことが多い。
そしてこれが長期化すると、左右共に実、もしくは左右が逆転することがある。
これら一連の変化と、陰陽・気血の消長との関係において、現実的に把握する上で何が起きているのかをイメージすることが難しかった。
この問題提議の答えは、自分の中で随分と長い間くすぶっていたのだが、現時点での自分の見解を開示して、読者諸氏のご意見を期待したいと思う。
日常我々は、陰陽、緊張と弛緩の消長と転化のサイクルで生きている。もちろん自然界も同様である。
緊張時は、気は長じ、血は消である。
逆に弛緩時は、気は消じ、、血は長じる。
昼の活動時に休憩と食事をとるのは、気を治め血を養うためである。
昼の活動と睡眠も、同様である。
気血の消長の様を、気機として捉えると、陽である昼は内から外へ、下から上へのベクトルとなり、陰である夜はその逆になる。
気滞が存在すると、この上下・内外の気機が失調するわけであるが、左右はどうなのであろうか。
気が下から上に昇るには、腎の蒸騰作用、脾の昇清作用、肝の昇発作用がそれぞれ協調して行われる。
逆に、気が上から下に降りるためには、心火の下降作用、肺の粛降作用など、胸陽が穏やかになり下降し、相対的に腎の納気作用が高まり、胃気を始めとする腑気の下降作用が協調されて行われる。
この上下の気の動きには、必ず左右差が生じる。
上方向の気である肝の臓象は、左三葉、右四葉の合計七葉である。
下方向の気である肺の蔵象は、左右共に四葉の合計八葉である。
このことから帰納されることは、上方向の気は、左で鬱しやすく、下方向の気は右で鬱しやすいということである。
してみると、難経十六難の腹診に記載されている、左天枢付近を肝とし、右天枢付近を肺としていることとも符合する。
しかも肝肺は共に、葉に象(かた)どられている。
このことの意味は非常に示唆的で、その時々の外部環境変化と内部環境変化に応じて、自在に動きを変化させ対応する、肝肺の特性を葉を以て表現したものである。
内外の環境変化に対して、気滞を生じるとまるでロックがかかったかのようになり、上下だけでなく、左右の変化が次第に大きくなっていくのである。
さらに難経三六難に端を発した命門学説における各家の論説の中で、筆者は「両腎の間が命門である」と主張した趙献可の説を取る。
さらにまた、夢分流で述べられている、右命門(腎陽)、左腎水(腎陰)もまた臨床的に符合する。
筆者の考えでは、左右の腎は共に陰陽を携えているが、どちらかといえば右腎に腎陽の状態が現れ、左に腎陰の状態が現れやすいと理解している。
その間にある督脈上、第二腰椎下命門穴に腎陰・腎陽の消長のカギがあると考えている。
左右の枢は、任脈と督脈であることはすでに何度も述べている通りである。
従って、濁陰の通路である任脈よりもむしろ、清陽の通路である督脈を丁寧に、詳細に観察することで見えてくるものが必ずあるはずである。
筆者は、この確信を元にして、つぶさに観察を重ねてきた。
例えば、肝鬱気滞と判断される疾患に対して、四支の経穴を用いて理気を図っても、期待した通りの結果が得られないことがある。
このような場合、背部兪穴の左右さの大きいところの督脈上の経穴に補瀉の手を加えることで、左右だけでなく全体の気の偏在が瞬時に解消されることがある。
また刺針後、部分的な気の偏在が残る場合、陰邪の存在などさらに詳細に病理を構築する手がかりともなる。
このように一度に多く刺針するのではなく、あらかじめ詳細に切診を用いて身体の気の偏在をしっかりと認識し、その上でどのように気を動かすと良いのか術者の心根にしっかりとした意図を持つことが大切である。
その上で、一鍼を下した後の変化をしっかりと捉えると、患者に対する認識はさらに深まり、病の構造も明確になると筆者は実感している。
加えて、七情の気の動きを背部に映して診ると、患者の内面までもが覗い察知することができる。
読者諸氏のご意見を、願っております。


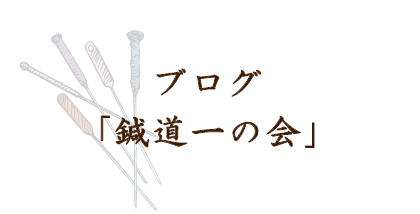
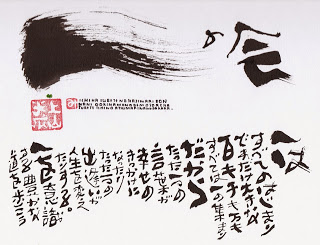


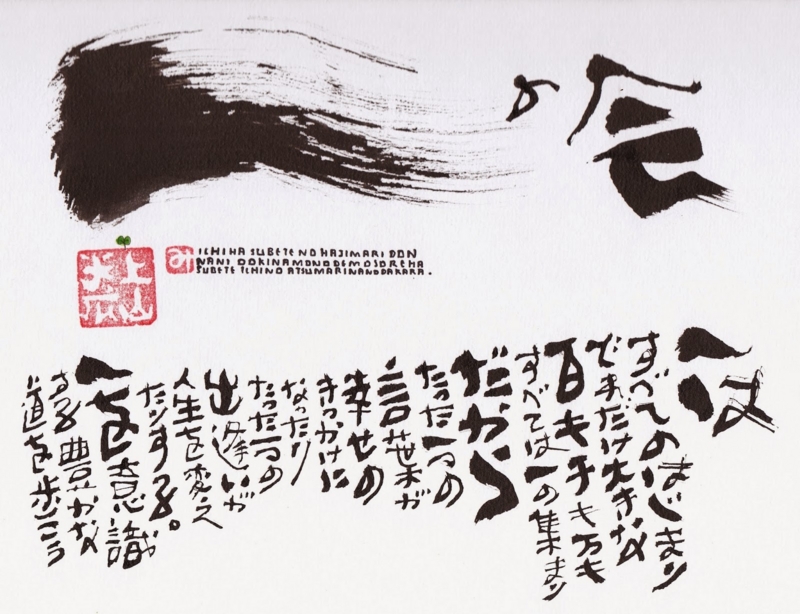

コメントを残す