今回投稿しました動画は、7年前のものでして個人のアカウントでしたので、「鍼道 一の会」に改めて投稿しなおしました。
今改めて、見直してみると当時お話した路線を維持しつつここまで来たのだなと、感慨深い感じがしております。
我々鍼灸家は、直接目に見えない「気」を扱うわけですから、理論だけでは臨床の役にはならないのですね。そうはいっても、理論は全く役に立たないのかというと、そうでもないのです。
理論は筋道ですから、気の動きを捕まえる際に当たりをつけるのには、非常にありがたい地図のようなものですかね。ですが、最終的にはやはり、術者の感性によるところが非常に大きくなって参ります。
長年、筆者が手掛けてきた黄帝内経・素問の意訳も、さらに実学として臨床に役立つ解説をこれから書き進めます。
すでに「三才で読む上古天真論」①~③を投稿しておりますので、よろしかったらお読みくださればと思います。
「一の会」では、術者の個性を大切に致します。
四診にしても、自分の得意なところ、観やすい角度を自覚してもらいます。
術者一人一人、感性と在り様は異なっているからです。
また人は、心を持っていますので、メンタルと体の関係もその都度話題として取り上げています。
また動画の中で、患者さんと接して、「なぜ?なぜ?と深めて追及していくと、必ず矛盾が生じる」と述べています。
例えば、女性に多いのですが、手足やお腹が冷える、いわゆる冷え性を訴える方がいらっしゃいます。問診を進めていくと、冷え性であるにもかかわらず、アイスなど冷たいものを好まれる方がいらっしゃるとします。
身体が冷えると訴えているのに、冷飲食を欲するのは、矛盾してますね。そうしたら、この矛盾をさらに問診で、切診で解いていき、例えば気滞で表は冷たいが、裏では熱が鬱してると認識できれば、矛盾が解けますね。
さらに「一の会」では、人体を心を持った3Dの立体として認識します。これに時間軸を加えて4Dにしてみると、患者さんが病にならざるを得なかった人生上の問題が観えてきます。こういったことを踏まえて治療することも、治療家としてはとても大切なことです。
「一の会」も現在は、代替わりをしまして、現在は稲垣会長・江見副会長体制で行っております。
筆者・金澤の鍼は理論的根拠を備えつつ、感性を中心とした治療を行っていますので、実際に観て覚えてもらわなくてはなりません。
筆者の治療は標準化できませんが、ここまで歩んできた道のりは開示できますので、東洋医学に則した自分流の鍼を見つけて頂く資材に成りうると考えております。
また長年一緒にここまで歩みを共にした、稲垣会長は、独自の脈診術を編み出し、標準化に成功しています。と言っても、繊細な脈を取る感性は必要ですが。
そして江見副会長も、独自の視点と術を保持して鍼を行っております。
一見、「一の会」は、それぞれバラバラのようですが、東洋の医学思想を根にしているので、意思疎通には何の問題もありません。要は、方法論が異なるのみだからです。
理論で人を癒すのではなく、術者と患者様との「気」の響き合いで人を癒していくのが、東洋医学であると筆者は、固く信じております。



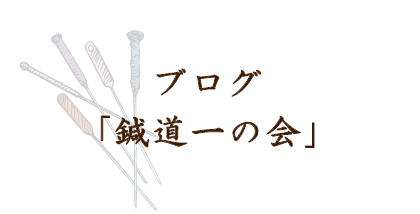




コメントを残す