諸書に健忘と云う病門を立て、心疾なり又、痰なりなどと有り。是は平生通りにて病もなくて居ながら今の事も忘るる病なり。憂喜も知れず、今食事しても忘れて何故に食事を引たるや、早く呉れよと催促するに至る。
愚なること小児の如く、大癡(だいち)の如き有り。又、老耄(ろうもう)と云う。是と同因なれども元来の天賜(てんし)にて元気によろしき所ありて老来しても一命盡きず、壮年の時より心労を重ねたる人に在り。是は死せずに長くつづく人多し。
予、数々試るに中風の未発にて常に機会を以て処世する人、又は劇務(イソガシキ)の人に多し。是れ亦た前に云う、智慧工思其の分を過して中風の一症を引き出されて早く見(アラワ)れたるなり。即ち健忘は中風中の一症にて別に門を立べからず。
さて中風は夏日は猶更不遂の方は手足ともに浮腫を催すものなり。敢えて腫気にもならぬものなり。
亦た脚気を病むに中風と同じく併病するあり。其の症、中風の軽きにて両脚に腫をなし、歩行便ならず、或いは半身麻痺して腫れ、喘悸し心下に蓄水あり。脚気の一名に緩風と云うは此れを指すの名ならんか。
夏に至れば年々此の如くになり、冬に至りて止むも有り。此れにも亦た放心して物忘れして精彩偶然になる人有り。中風脚気の合病なり。其の多き証に従て治すべし。先ずは脚気の治多し。灸などして本証は退けども健忘は止まぬもの有り。
又傷寒の後、健忘を患ること有り。此れも行々年月を経て中風の機をあらわすなり。
「傷寒論」に瘀血ある人好みて忘ると云うことも見ゆ。既に傷寒の部に説きたりき。
中風は中年以後の病なれども小児にも有り。少壮にも有り。小児の中風は肝積或は疳癖などと称すれども口眼歪斜して言語爽(サワヤカ)ならず、口涎を流し、又、十五六の童の病(やみ)しも時々見受けたり。
俄(にわか)に発して半身偏枯口眼ゆがみ、大癡(アホウ)の如くになる。此れ地の俗、此れを神に遇(あい)しと称するもの、即ち中風にて精神守りを失(うしない)せしなり。
老人ばかり中風するものに非ず。然れども少壮は治しやすし。其の因は如何と索(もと)むるに積塊の有る人、是れを病む。
其の塊、左に在れば左を不遂し、右に在れば右を不仁す。常に腰脚を痛み疝気持と云いし人の中風したるは、兼ての形を帯びて有るものなり。
疝積と云うも又、瘀血凝結して塊を結ぶ所にて同因なり。其の始めは悉(ことごと)く胎毒の因に係る。
「素問・腹中論」に「帝曰.人有身體髀股胻皆腫.環齊而痛.是爲何病.岐伯曰.病名伏梁.此風根也.」
<帝曰く。人の身體・髀股・胻、皆腫れ、齊を環(めぐ)りて痛む。是れ何の病と爲すや。岐伯曰く。病伏梁となづく。此れ風根なり。>とあり。
是れ即ち積塊のある人、中風の因となるの事なり。後世絶て此の事を唱る人無きは何ぞや。五臓六腑、諸不足の説のみ専らになりたる故なり。凡そ万病ともに実に属する者、什(十)の七八にて、虚に属するもの什(十)の二三なり。
又始め左の不遂したるが一通り愈(いえ)て再復する時に右へかわる事あり。是れは其の積塊の結する所、腹内にてかわりたるなり。
又、男は左、女は右を不遂すると云うは、例(たとえ)の配合にて積塊のある方不遂す。男女にて左右と極むるに非ず。又、男の右を不遂し女の左を煩(わずらう)は治しやすしと云へども、其の治しやすきは病の軽重にこそあれ。
老人他の大病を患る最中に中風すること有り。重きは知るれども軽く併病するは、心得なければ見付けかぬるものなり。
婦人産後に中風することあり。俗に血中風と呼ぶ。其の證候、常に中風に異ならざれども血熱を帯びて治しにくし。多くは小便不利して腫をなすもの有り。乳汁の多少を見などして吉凶を占う。
是れは分娩にて血気俄(にわか)に動き腹内も急に透る所出来る故に、件(くだん)の癥塊の動き出たるなり。又悪露多く脱血して発するも同意にて、産に引かれて老来の病を早く発したるものなり。
其の治不治に至ては、常の中風と異なることなし。又、産後痿癖すること多し。中風と因を同すれども猶産後の病に語るべし。
凡そ痿癖と云う病は「史記」に「痿人起を思わず」と有りて、註に「痿は行くこと能わず」、「前漢書・ 賈誼傳」に「辟(へき=かたよる)に類す。且つ痱(ひ)を病む」と。註に辟は足病、痱は風病と見ゆ。「素問」に足痿とあり。其の症脚気にも似、又、中風にも似たり。
脚気に属すべきは両脛に腫を催すものに脚気の治にて愈る有り。外感の後に寒熱退かずして脚麻痺して漸々に覚なく腰のたたぬも痿と云うべし。
是は足の指を動かさせて見るに少しは動かすことのなるは軽しとし、重きは指頭少しも動揺することならず。手をそえて動かすときには筋絡へ拘痛するも有り。日月を経れば寒熱も止(やみ)て、他は苦しむことなく平臥す。甚だしきは手臂の拘攣するもあり。
其の不経なるが為に大肉削(ケズル)が如く、飲食も味変わらず、言笑も常の如くに見ゆ。
是れは中風と同因にて癥塊瘀血の因に係る。桂枝加苓朮附湯、甲字湯、鼈甲湯(べっこうとう)等の類に附子にも、又、烏頭(うず)にもする。芍藥甘草附子も用ゆることなり。ゆるむとしまるとにて異なるなり。又委中を刺し出血 して十の六七を治す。凡そ委中を刺すの法は嘗(かつ)て著す所の「瘈狗傷考」に詳(つまびらか)にすれば是れを見て行 うべし。
此の痿などを中風に属せば種類多くなれども、「深師方」に三十三種の風、又「千金」に六十四種風とも百種風とも、又「張文仲方」に、風に一百二十種有りと見ゆ。其の名目に至りては一々に数え盡(つく)しがたけれども、大概中風の中気のと云う名は直に解すべし事。
かわりたる名は、風痱(ふうひ)、風癔(ふうおく)、風懿(ふうい)、風痺、風〇、曳風(えいふう)、猥退(ワイタイ)、頑風(がんふう)、唖風、暗風(あんふう)、簷風(センフウ)等、此外にもあるべし。
爰(ここ)に至れば博く書を読まねば眩惑し、その名に臆する所なり。治療に臨みては例の通りにて一百二十種の風を一百二十方にて治す事にはあらず。一方にて一百二十種の風を治す。爰(ここ)が大事の見分けなり。其の病因を知らねば一方に取り扱うことならず。見証にてならぬ場にて「華陀の方、数首に過ぎず」と云う所なり。
痿を中風に属するの理も、味(あじわ)へ知るべし。大病の後にも痿することあり。是は血気未だ復せざるなり。
別(わけ)て小児は大病ほどに無くとも腰の立ぬもの多し。日月を経て調へば愈ゆ。是も中風に属すと云うべからず。
又、麻疹後に痿するは皆浮腫を帯(おび)て腨(せん)の大筋索急にて按ぜば痛む。是れは脚気に属するものにて痿癖には非ず。八処の灸に越婢加朮或は木防已湯の類、檳榔湯などの主る所にて皆愈えたり。是も痿とすべからず。
又、陰痿と云う名、「病源論」に出づ。痿は足のきかぬ名をかりて陰具のきかぬに用たるなり。是れには天賦にて壮盛の丈夫、女に近づくこと能わざるものあり。病にあらねば中風にかかわりしことに非ず。
又、半途より陰萎になるは病にて是は気癖に属すべし。「本朝醫考」に宗嗣露蜂房を奉りて宇多帝の陰痿を治せしことを記せし故、是を試みるに奇験あり。然(しか)れども気をくじきて癖つくなれば、其の気を転ずるように治すべし。其の人を見て権変を行うべし。
一士人、背痛甚だしく寒熱日を経て痿癖して起つこと能わざるのみならず、疼痛して転側しがたし。葛根加附子を与えて寒熱漸く退けども痿は始(はじまり)の如し。数医の手にて治せざる故に又、予に乞う。 桂枝加苓朮烏頭を用ゆ。出入三年にて痛み去り、起歩するに十四椎突起して亀背になりたりき。
又、昨日まで何の事もなく居たるに、俄然として腰以下痿弱し、他人の身の如くになるあり。是は「素問」に痿厥と出たる病なり。其の腰以上は常にかわらず、飲食氣力少しも煩わしきこと無く、只立つことはならず。是迄(これまで)見たる病人、一人も治したること無し。
又数年を経ても死せず、試に人手をそえて引立るに両脚軟弱にて縄の如くによれて、坐せしめんとすれば両足の跗もつれて解ず、手をそえてはづす。骨無きが如し。後世是を痿輭(いなん)脚軟などと名づく。
一士人の子、十六七歳、俄に洪水に遇て床を高くするとて働けるが、次早忽然として痿して立つこと能わず。数医を延(ひ)くに皆治せず。
※延(ひ)く…まねき入れる
其の人腰以上は平人の如く、足は他人の如し。囲碁書写をして日を消す。士人子孫の断絶を患て妾を買うに数子を育す。
又、仙波湖上に隠居せる人の侍童十四五歳、一夕雨晴水高くして陸を浸す。童喜(よろこび)て船に乗して槽廻(おけまわ)す。翌朝、俄(にわか)に痿して匍匐(ほふく=はらばいして進む)することも能わず。数医を迎るに治せず、三年許にて死す。
又、一士人夜燕(夜宴)す。小解せんとするに、起つこと能わず、坐中其の病なるを知らず、皆笑う。一時ばかりにて能く起つ。深夜皆散ず。
玄関を下ると又痿す。酔ると思て人々休息せしむ。暫くして又起きること得て辞し、帰るに常に異なること無し。
是より二三日、四五日に一発す。仍(より)て来て治を乞う。其の人、気力動作いささかの障りなし。予以て為す、疝なりと。烏苓通気加烏頭を与えて治す。既に六七年を経たり。再発せざるや其の後、何の沙汰も無し。
兼ねて中風を催せし人は常に能く眠る。狂を催す人は一切に睡ること能わず、油断すべからず。中風の催しは半身不経して肌に糊のつきて乾着したる様に覚ゆ。甚だしきは麻木不仁す。麻と云うはしびれること、木というは覚の無きこと、不仁と云うは梶原性全の「頓医抄」に「人はだならず」と訳せり。人何のわけもなくしびれるは中風か、又は脚気の催しなり。
又、堺を立て痺れる。是を死肌と云う、癩病の漸(ぜん=じわじわ進む)なり。血色を察すべし。虫のはうが如くにて掻きても知れず。又、指の一二本屈むると手をそえねば伸びず、痛くも痒くも無きは中風の漸なり。又、肉脱して細(ホソ)るは癩もあり、又脚気にも手指の拘攣することあり。混ずべからず。
麻葉を食せば一身麻痺して歌哭癲狂すること曼陀羅花を用いたると同じ。故に麻と云うや、またしびれる故に艸に名付けて麻と云うや。
又、歩行する度々つまづくは何れ脉弦大にて力を帯びて熱を催したるやと見え、又眩暈して耳など鳴り、項背強り、精神爽やかならず、何か思慮して居るかと云う形にうき立たす。或いは欠(けつ=あくび)を沢山する、健忘の姿を加えるもあり。皆中風の候なり。
壮實の人、元気まかせに巧思・労神・淫酒過度して老来にて中風するを早く引き出すなり。
又、執筆するに仮令(たとえ)ば文字を書くに、思い掛け無く筆の走り出すことなどあるも中風の漸なり。
「金匱・中風篇」に「防已地黄湯、病狂状の如く、妄行独語休(や)まず、寒熱無く、其の脉浮なるを治す」とあるもの、今考え合わすれば、父母中風すれば子孫も中風す。
乱心するも亦た此の如く、父の狂するに子も狂し、又近縁兄弟の狂するは度々見たり。
一旦其の狂を治して平復し、数年を経て中風するものあり。又狂の半より中風せしも中風の半より狂するも見たり。
狂する者は中風の放心して忘れ、或は泣き、或は笑い、或は怒りなどすると同機にて、狂と中風とは同病かと思う。健忘は勢いの柔なるもの、狂は勢の剛なるものならん。
健忘の甚だしきは狂に類して気癖にも似るものなり。気癖も狂の属なり。
一富農の妻、手足拘攣して行歩なり悪く、口唇麻痺して常に之を撫る。食味は相応なれども口に唾を吐すること甚だし。日夜其の病苦を傍人に告げて、且つ又死せんことを患(うれい)て落涙す。「婦人蔵躁悲傷者甘麦大棗湯」の証にも似たり。虫積にも似たる所あり。
上衝・眩暈、医を見ては猶更に病状を告げ 訟(うったえ)ること、同じことを幾回も云う。終日之に対せば終日同じことを言う。又睡中に死せんことを恐れて安眠することならず。看病の人の多きを欲す。先づは静なる狂なり。
年余治せず。予に乞う。中風なりとして桂枝加苓朮附を与う。善悪なし。唾を吐するは日々六百枚紙にて不足と云う。少し嘔の気味もあり、唾を呑めば悪心するを恐れて吐くと云う。小柴胡加鷓胡(しゃこ) を与える、依然なり。安神丸兼用、三黄湯、半夏瀉心、帰脾湯の類、皆効無く、一日之に教えて曰く、
「唾は是れ津液なり。此の如く吐せば血肉枯乾し痩せんより外無し。生を求めば吐くべからず、道家には玉泉と云う、之を飲むこと長生の法なり」と。是より一切に吐唾することなし。始め左右拘攣したるに、此頃は唇も舌も半身甚だしきことを覚えると云う。
又、医を転ずること三四輩にて治せず。又予を迎う。 偶(タマタマ) 「経験筆記」を読むに沈香天麻湯の症、必至と符合す。容子(ようす)を見るにも及ばず。此の湯を用いんと、常に使わぬ薬など有れば用意して速に調進す。手に応じて治したれども拘攣は退かず。
一門人の娘、年十八、新嫁(しんか)して未だ久しからず。午食しながら卒倒す。近所の医、集まりて湧泉、労宮に灸するに応ぜず。又、一医を引くに相議して曰く、是れ灸小さしと。更に大灸を以て数壯に及べどもさめず。兎角に難治なり、多く灸するの外なしとて、数刻の間灸すれども脉も絶えず、呼吸も有る故にいやが上に灸す。夜に至て退屈して灸を止むるに猶死せず。
其の夜、守りみるに半身は手足ともに運動せず。能くみれば口眼も正しからず、始て中風なることを知り、予を迎えて治せしむるに、一二日を経て精神頗る復するに、彼の灸痕膿を為し、臭気一室に満つ。且つ疼痛して不遂のみならず、手足を動揺することならず。
又、数十日を経て本証の中風は治したれども艾灸(がいきゅう)筋絡を傷りて掌中攣して指を伸ることならず。之を治するの法なし。終身の廃人となれり。慎むべきことならずや。
一士人夏月、殺生に出たるに炎熱に堪えず、人家に入て酒を命じ、晩涼を待(まち)て仮寝す。醒て出たるに供人等、主人の口眼歪斜したるを見て大に驚く。本人は嘗て知らざるのみならず、何も苦き所無き故、猶殺生せんと云うを押留め、駕(かご)を命じて帰る。
速に予に乞う。六脉平和、他に煩わしき所なし。是は中風の一症を発したるなり。八味順気散を投じ、十日許にて口眼舊(旧)に復す。
疾風飛砂の時、眼を瞑するに一眼は眼胞の閉ること遅き故に、塵埃(じんあい)眼に入て涙を流す。又十日許にて全快す。
此の症、度々見受けたり。老来にて発すべきを早く引出す故、軽く一症を見(あらわ)すなり。
又一人肩の上に大痣(だいし=あざ)あるを抜くとて灸するうこと七八壮、乍(たちま)ち口眼灸せし方へ牽釣(けんちょう)す。口涎を流し、飯するに米粒をもらす。
是は中風に非ず。ゆるむ時は治すべしと。則ち桂枝甘草湯を与う。数日ならずして平復す。
鼈甲湯 積聚門に見ゆ
甲字湯 二方 烏頭を加える或は附子を加える
三黄湯 黄連解毒湯 参連白虎湯 熱芋癇と云う所より用ゆ
腎気丸 大青竜湯 葛根加附子湯
参連湯 参熊湯 八味順気散 烏苓通気湯
諸病ともに卒倒したる時、蘇香圓などを用ゆるに、牙関緊急して入らざる時に皂莢末(さいかちまつ)、半夏末を鼻孔より吹入るること有り。
口より入らざる故の手段なり。牙関も緩みて有る時に鼻より吹たる医を時々見たり。此の如きは心得居くべきことなり。
中風の灸なりとて、少海、温溜などへ灸すること有り。微(かすか)に麻するは治すことなれども、手の麻するは手に目を付けて治するは悪し。
其の根は腹に在り。中風の灸は、予未だ其の経験を得ず。後日を俟(ま)つ。
卒倒したる時、人中、百会の灸、并に出血のことは是れに異なるなり。
医事小言巻之二 畢


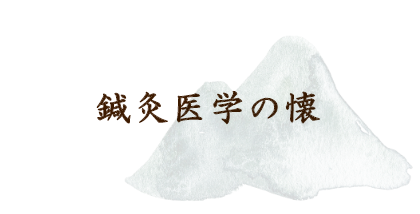



コメントを残す