叢桂亭医事小言 巻之二
原南陽先生口授
門人 常陸 大嶋員 筆記
東都 山形豹 校正
傷寒
傷寒は別て治療の六ケ敷(むつかしき)ものにて此の治法に熟すれば諸病ともに自由するは別儀(べつぎ、さしさわりの意)に非ず。表裏の証候を知る故なり。
仍(よっ)て傷寒論に熟して仲景氏の方法、古人の真面目を知りて医をなすべし。傷寒と題せし名目よりして論中の中風の名、三陰三陽の篇目ともに諸医書に論したる見解にては通ぜず。
桃井寅の古訓に、仲景の論を学ぶには今日まで習いたる事を捨て、新眼にて読むべしと云うは尤もの説なれども傷寒の外に温病有りと云うは非なり。夫れ傷寒と云うは疫疾の事なり。
陰陽大論に曰く、 「冬時厳寒なり。萬類深く蔵ず。君子固密するときは則ち寒に傷られず。之に触冒する者は乃ち傷寒と名(なずく)る」耳(のみ)。
其の四時之気に傷られるも、皆能く病を為す。傷寒を以て毒と為す者は、其の最も殺癘之気を成すを以てなり。中(あた)りて即ち病む者を名づけて傷寒と曰う。即ち病まざる者は寒毒肌膚に蔵し、春に至って変じて温病と為し、夏に変じて暑病と為す。暑病は熱極りて温に重すなりとある故に、傷寒は冬の病名とする事、古今の定名なり。
然(しか)れども、此の眼を以て傷寒論を読むは悪し。
此の時代に疫を傷寒と唱えたるにや、後漢の崔寔(さいしょく)と云う人の政論にも傷寒の字見ゆ。此外に儒書に傷寒と云うこと見あたらず。
又傷寒論に重きを傷寒とし軽きを中風とす。是亦多くの医書に出たる半身不仁の中風とは異なるなり。又三陰三陽と云うも経絡流注の義に非ず。
素問熱論の序次に合わせんことを欲して、後人太陽の次に陽明を移せしならん。太陰少陰厥陰と三陰に対する故に、太陽少陽陽明とあるべきなりと云う説あり。至りて宜しき考えなり。
明の呉又可(ごゆうか)の『温疫論』に、傷寒は少なくして伝染せず、温疫は多くして伝染することを論じ、邪気も一種の雑気なり、傷寒と異なるなりと云うは、是も仲景の書を常の眼にて見たる故に誤りなり。仲景何ぞ少き傷寒を以て論ぜんや。
且つ仲景の世に疫疾の多く行われたるは、序文中にも宗族多く亡(なくせ)しことを記せり。
是れも傷寒にて死たるにて疫には非ずと云はば、又仲景の時代を考(かんがえ)見るべし。
建安中に別して疫疾流行したる事にて、呉の孫権、合肥城を圍(かこ)むに、此時に疫疾多く士卒死亡すること有り。
又魏の文帝の呉質に与(あたえ)る書に曰く、
「昔年疾疫親故(しんこ、親類の意)、多く其の災いを離(かが、罹患の意)る。徐陳應劉(ちんじょおうりゅう、四人の人命の意)、一時倶に逝(せい)す」とあり。是皆仲景時代の事にて、当時疾疫多きを知るべし。
此の外『後漢書・禮儀志』に、臘(ろう 年の暮れ 陰暦1月2月)に先だつこと一日、大に儺(な、鬼を追う払う儀式)す。之を逐疫と謂う。
其の儀、中黄門の子弟十歳以上十二歳以下、百二十人を選して、振子と為し殿中を逐うこと有り。
此外(このほか)前後漢の間、疫を恐れ剛卯などと云う事を行うの類、毎挙(まいきょ、枚挙の意)するに暇あらず。
又、和漢一般に歳暮年頭より五節句に至るまでの儀式は、皆疫を除くの事なり。叢桂偶記に詳(つまびらか)にせり。返す返すも仲景何ぞ其の多き疫を置きて、少なき傷寒を以て論を著せんや。
『肘後方』に曰く、「傷寒、時行、温疫、三名同じく一種耳(のみ)。而して源本小異なり。」
又貴勝(きしょう、勝つことをとうとぶの意)雅言(がげん、洗練された優雅な言葉の意)、総て傷寒と名付け、世俗因りて号して時行と為す、と見ゆ。
又『小品方』に「傷寒は是雅士之辞。天行瘟疫と云うは、是れ田間の号耳(のみ)」。
又『張果医説・古今病名不同篇』に曰く、「古人経方雅奥多く、痢を以て滞下と為す。躄(へき、いざり あしなえの意)を以て脚気と為し、淋を以て癃と為し、実を以て秘と為し、天行を以て傷寒と為す」と。
此の言、「以て千載(ぜんざい、千年長い年月の意)聾聵(ろうかい 聴覚障害)を以て発す可し。」とあれども、疫と云うもの正名にて、其の外の名は医家にて名付けたるなり。
如何なれば正史に疫と記す。是は國政に過失あれば天地の気候、其の正を得ずして、人民疫疾を患(わずらう)るに至る。人君をして其の過を改めしむんが為に史官正く記するの故に疫を正名とす。
疫の字義は其の流行するに、あまねく戸々に病て徭役(ようえき、国による強制労働の意)にあたるが如くなる故に、殳(しゅ 杖で人を撃ち殺す)に从(したが)いて疫とは云うなりとみえたり。
是乃ち伝染の病なり。呉又可(ごゆうか)の説、益々信ずべからず。傷寒中風のことは是も偶記を読みて知るべし。
さて何故に仲景の書は今の眼にては読みがたきとなれば、古は今の様に素問難経を以て学びたることはあらず。別に伝有ると見ゆ。史伝に載(のせ)たる古医の事を見て考え合わすべし。
医和の惑蠱(わくこ)、医緩の膏肓篇、扁倉伝の医論。是れ今の医家の説と合わせず。尤も此の類は儒者の書たるもの故、医家の説にあわず、虚言なりと云う説もあれども、史を作るほどの人、医のことも少しは知りて文作はすべし。
若し医のことを知らざるほどならば、天官地理日者と、者の類も虚言多からんや。遙降(はるかくだ)りて褚澄(ちょちょう)の説さえ吻合せざる所あり。況(いわん)や仲景の時をや。
しかるを今の素難の説に合わせんと註解するは不案内ならん。是を知らざる世々の註家、是非に取り合せんと其の文を入れ替え、章句を改めなどして却って其の真を乱る。
此の故に今風の眼にては読みかねるは傷寒中風の名目のみならず、是を以て見れば素問は後漢の涪翁(ふうおう)の作ならんと云う説などは面白からんか。
呉又可(ごゆうか)曰う、陰陽大論にある通りにて冬寒・春温・夏暑・秋涼は四時の正気なり。冬を傷寒とし、春を温病とし、夏を暑病とすれば秋涼に至りては涼病と名づけべきに、涼病とは云い難きと見えて湿証を以て州塞(フサケル)するは謬妄(びゅうもう、根拠がなくでたらめの意)なり。
又寒に中りて即ち病まず、春に至りて変じて温病となり、夏に至りて変じて熱病となるとあれども、然れども風寒のやぶる所、最も軽きものを感冒とし(引風なり)、重きを傷寒とす。感冒の一証は至りてかるきものにてさえ頭痛、身痛、四支拘急、鼻塞、声重、痰嗽、喘急、悪寒、発熱して病む。
人身、邪気を隠して容(い)るべき所なし。況(いわん)や冬時厳寒に傷らるるは軽き事にあらず。夫れが反って蔵伏して時を過ぎて発せんや。
凡そ人身は十二経絡・奇経八脈にて百骸を栄養するに、其の気少しも滞る所は麻木不仁し、造化の気、寸刻も運(めぐ)らざれば仆倒(ぼくとう)す。
又風寒の人を傷るは肌表より入るに、寒邪既に身にあたり、其の毒肌膚に隠れてある中繊毫もしれず。飲食・起居・神思、常の如くにてあるべき理なし。春になるまで皮膚の間にあるべきは、如何に霊異なりとも余り合点せず。
此の理を以て之を推すに、冬寒を受けて春に至りて病み、又夏に至りて病むの事は無き事ならんと。予按ずるに冬衣服薄く或いは食に乏しき貧人は、必ず春に至って疫を患う。是は冬寒に傷られたるに似たり。
左(さ)れば冬寒気に日々の保護を失い血気も是が為に充満せずに居る故に、冬の中に病むも有れども、日月の長き間彌(すでに)血気を傷る。故に春に至って邪を受けるならん。邪気は新たに受けるとは見ゆれども皆此れ臆度(おくたく、おしはかるの意)にて眼前に見るべからず。猶佛家の前世の未来の説の如し。
今世神霊妙手と云う人有りて冬時に其の人を見て、春に至りて疫を病まん、夏に至りて熱を病まんと前年より知るならば、其の論説臆度と云うべからず。されども今日まで斯くの如き上工の医に逢いたること無し。
さて又冬に受けたらんも春に至りて新たに受けたらんも、治法に於いては別に手段あることにあらず。故に過法の因縁には構いなし。故に吾が門にては其の病みつきてよりの証候内外を見はづさざるを専務とす。空理を求むるは、予が好まざる所なり。
傷寒頭疼悪寒すると手足解怠し、或いは腰痛脉数鼻息あつく、やがて熱になる。是には只の引風も有り。されども疫熱なれば見所よりは気分もあしく、熱伏して表に浮(うか)まず、腹候もちりぢりとして格別なるものなり。
脉浮にして惣身熱し、腹候して一応はちりぢりと掌へ熱すれども、暫(しばら)く按ずれば始めの手あたりよりは薄く、猶心を用いて候するほど常の肌に似て汗を発せんとうるおいも有れば、苦悩するとも大熱にはならず。
又左のみの熱にも非ず食も無理にはなり、床にも未だ着(つかず)に両日も催し、漸熱の強く成るも有り。是は見分けに巧者の入ることにて望聞問切の四診を以て弁すべし。
又労熱にもならんかと微悪風、飲食を好まず床に着きもせず、脉弦数にして肌は悪熱し数日を煩うこと有り。俗人皆すすめて弱気もの哉、病にしかるるぞとて強いて浴櫛(モクシツ)し、或いは見物などを催し、却って熱気いやまし解しかねること有り。彌(いよいよ)労熱なりとして治するに随い大病に仕立て、或いは四華の灸などにて益々難治にする。是は軽疫にてあるなり。
心を付けて診すれば労脉にはなく外証の所多きものなり。さて舌上をみるべし。必ず胎をかけて有るものなり。
年により微疫の多きこと有り。兼ねて心得あるべきことなり。初起の治方は上衝頭痛脉浮にして悪風寒熱、汗の出るは桂枝湯。項背強らば桂枝加葛根湯。脉浮緊と、ひどきは熱強、悪寒、頭疼、身痛、喘咳するには麻黄湯。項背強には葛根湯。寒熱しばしばに往來して咳するは桂枝麻黄各半湯。咳するは小青竜湯。渇するは大青龍の類撰用す。発表の効届かざるは、狂躁、譫語、煩渇等の諸悪証を見(あらわ)し、死生相半するに至る。
初心にては証候を詳(つまび)らかに具せんことを欲して度々方を転じ、或いは時々下し、或いは芎黄散の類を兼用するもの大いに仲景の真を失う。
凡そ表証の有るに下すは仲景の規矩に非ず。誤下すれば心下に滞(とどこおり) 出来て痞鞕・支結、甚だしきは結胸などになるの類、往々仲景論じたるを知らざるは眼光の紙上に及ばざるなり。何れにも発表を専らとするなり。
傷寒治療の助けになるものは呉又可(ごゆうか)の温疫論なり。以上論ずる所までは用ゆべからず。表証既に解せずして陽明に至るものより以後は、呉氏の論至りて実地にかけて甚だ宜し。千載の一人とも賞する可し。
然れども不内不外募原と云う所に邪気の居と云う説、又達原飲と云う方を用ゆるの論は、建言家の常態にて深く怪しむべき事に非ず。発表の手をゆるむるは仲景の方に非ず。是全く傷寒温疫を両途に見たるの誤りなり。表証に裏を攻むるは仲景の規矩に非ず。
先ず飽くまで発表して而る後に夫々の証に随うべし。世人の治法を見るに二三日も発表すれば表証の有無に構わず柴胡などにす。是れ大いに非なり。
表証の盡きざるに此の如く手を引くべからず。発表の手当(テアテ)届けば狂騒譫語に至らしめず、太陽にて邪は打ち止まるなり。此の手当不届きなれば陽明まで攻め込まる。然れども邪、陽明に屯(たむろ)せば十分治し易く、勝ち軍(いくさ)ならんこと掌(たなごころ)にあり。
兎角(とかく)太陽々明二証のもの多し。又治しやすしとす。故に桂枝麻黄・大小柴胡・大小承気・白虎に治するもの多しとす。少陽の証は柴胡にて左までの事も無き故に仲景の論も短きなり。
太陽の証は頭痛・項痛・腰も痛み、強きは折れる様に痛むこともあり。陽明の証は目痛・眉稜骨痛・鼻乾く。
少陽は脇痛・耳聾・寒熱・嘔にして口苦し。大概は太陽と併病す。陽明の証に成るもの多し。
さて此の病を受ること自然に病むもあり。又伝染するも有れど其の治療は一つ事なり。邪気を深く受けたる人はあたりて直に病む。浅く受たるは飢飽・労碌(ろうろく、苦労して働くの意)・憂思喜怒にさそわれて発す。始めは悪寒し甚きは手足冷ゆ。
是は容器閉じて表へ達しかねる故なり。漸(ようやく)に通ずるに至れば中外皆熱になる。夫れよりは悪寒止む。表証の盡きたると云うは此の處なり。此時はしとしとと汗も有るものなり。
表に在る邪なれば一汗にて解せども、内に伏したるは何ほど汗有ても不益にて、元気許(ばかり)を疲(つか)らかす故、其伏邪のくつろぐを見合わせべし。
爰(ここ)に戦汗と云うことあり。温疫論に詳(つまびらか) なり。是は表気内へ通ることの、なるほど邪気くつろぎ、持分(時分)の積気は邪気の除くに随いて表へ通ずるの際に振戦し、瘧の悪寒の如く其の後一度に熱になると大汗流るるが如く、衣服を換(カユ)るほどにて脉も静かになり、身に熱無く神気爽(さわやか)に忘れたる如くに睡りて全快す。甚だ面白きものなり。戦汗を知らざる医は、大いに騒て参附などを主方すは以ての外。
悪しき戦汗にも死証あり。先ず戦して(振るえること)汗出ざれば、明日又戦すべし。其の時汗出ればよし。若し汗出ざるは中気の虚にて厥も止まず、汗も出ずして死す。傷寒論の厥深き者は熱もまた深しと云うは、此等に考え合わせ様も有らんか。
又戦して厥は止めども汗の無きは死するに限らざれども、急には愈えず、津液のめぐるを待ちてゆるゆると治すべし。 凡そ戦して痙を発するは死す。
門人奥州海辺に居る山形玄之と云う者曰く、潮時の戦汗は皆死す。引き潮の戦汗は邪盡きず、総べて潮時に戦するものなりと云う。余未だ試さず。他日を俟(ま)つ。
さて戦汗のことは傷寒論に出づ。又狂汗と云うこと有り。是も戦汗と同じく俄に大熱を加えて煩躁甚だしくして大汗を発し、身熱失うが如し。
以上、呉又可(ごゆうか)の論、熟覧すべし。戦汗の名は後来の事にて、傷寒論に曰く※1「太陽病、未だ解けず。陰陽の脉、倶に停。必ず振慓して汗出でて解く。但陽脉微なる者は、先ず汗出でて解く。但陰脉微なる者はこれを下して解く。若しこれを下さんと欲するは、調胃承気湯に宜し。」
又曰く、※2「凡そ柴胡湯の病証にしてこれを下す。若し柴胡証罷(やま)ざる者は復た柴胡湯を与う。必ず蒸蒸(じょうじょう)として振い、却(かえ)って復た發熱し汗出でて解す。」の類は戦汗の事なり。然る所、歳運の異なるにや。
予が壮時は戦汗狂汗の疫を常に治したるに、近来温疫論に説く所の疫至て、稀にて附子を用いて効あるもの多し。爰(ここ)に談ずれば紛れやすからんと、予が誤りを後に語らん。
さて伏邪退かず、今までの汗も止み熱も段々盛になり、昼過より毎日潮熱す。是れ陽気時刻と持合なり。是ぞ悪寒無く偏(かたより)に熱するもの多し。
或は微悪寒するも、或は強悪寒するも有るは、是は病人持ち前の陽気の盛衰なり。其の発熱すること久しきも久しからざるも、或いは昼夜純熱し、或いは早朝に稍(やや)醒るは、其の邪を受けたる所の軽重なり。其の変証に至りては、色々裏証が急に表証に成るもあり。表証ばかりにて裏証をあらわさぬもあり。内から陥るもあり、外より解するもあり。
外と云うは発班、発黄、戦汗、狂汗、自汗、盗汗なり。内に陥るとは胸膈痞悶、心下脹満、或いは腹中痛、燥結便秘、熱結傍流、或いは協熱下痢、或いは嘔吐悪心、譫言、唇黄舌黒、胎刺などの証は証によりて変を知り、変によりて治を知るべし。
一婦人疫を患い東洞流の医之(これ)を治し、一夜煩躁・慕(暮)熱す。其の医来て予が診を乞う。共に行きて見るに寸時も安からず。手足をなげうつ。
予、何薬をか与えたりけり、忘れたり。暁に至て安静なり。よく見れば一身薫黄の如し。熱解し身涼し。是は夜間にて黄を発したらんか。心も付かず目にも見付けぬなりき。三四日、茵蔯を用いて全快す。
傷寒は直に邪気を逐うこと専務なり。邪気退けば、其れに付たる諸証は悉く除くなり。此にいらざる工夫を付て、余り表発に過ぎるは、陽気を亡くすと。ややもすれば人参を加え、平日気虚したの、腎虚のと、取り越し過ぎた手当をする故、猛烈の病勢暫時に熱気内鬱し、舌も乾枯、飲食も通らず死に至れば、いよいよ虚弱にて邪気退かずと大剤の獨參湯或いは參薑湯などを用い、死に至れども暁(さと)らず。
是まで人参を用いても救いかねるは、能々(よくよく)弱き所有りけると療治違いに気も付かず、此の所へ一際(ヒトキハ)力を用いたる医は、人参を去りて薬を投ぜんとすれば、病家狐疑(こぎ、相手を疑う事の意)して決せず。富貴の人は猶更人参と言えば大事に取扱いて療治するぞと思う故に、十が七八は此に死す。悲しき哉。
虚弱にても邪気を逐(おう)までにて、持ち前の気血を損ずる薬と云うは無し。邪熱こそ血気を耗傷するものなれ。邪気退けば持ち分の平身になるなり。愈す虚損の所あらば、あとにて治方を行うべし。
邪気の未だ退かざるうちは虚弱な人ほど其の邪気に堪えかぬる故、速(すみやか)に攻めざればならず、譬えば邪気のあるは戦の最中の如し。其の族を退治せぬ内は静謐(せいひつ、静かで落ち着いているの意)せず、いかに補薬がよろしきとて戦のすまぬに礼楽を以て治めようとするの類なり。
礼楽は宜しけれども乱世には用いられず。治世になりたる時こそ人を教化するの道具なり。
熱病は初の内は少々宛(まで)は食もなれども、半ばころよりは食絶えて重湯位になる。是れ毒気愈(いよいよ)進て勢いくじけぬ故なり。食のなるは吉兆なれば悦ぶべきの一証なり。
妄語狂燥などするも脉の胃気と腹候にさはりなきは、絶食と強熱ばかりにては死すことなし。只初めの発表不足にては悪証多端に出るものなり。
傷寒は別(わけ)て持重(じちょう、大事を取って慎重にするの意)すること入用なり。必ず色々に方を替えて病候にうろたえること勿れ。持重する所、専一なり。
男女ともに治を異にせず。只熱にさそわれ経水の来たると来て去らずと、産後近きなどは欠(アクと)などして血熱を挟むことあり。下したる後、盡たらんと思う熱の残るなどは、極めて血熱を挟みてあり。加味逍遙散などにて効を取ることあり。承気の証と見分け肝要なり。
傷寒表熱速に解せず、日数を送り色々の証を発す。毒内に結する故、俄(にわか)に腹痛するあり。毒結などは下剤にてよし。大柴胡、大小承気、其の証に応じて用ゆべし。二三行下痢すれば腹痛止み、内気和暢して熱も退くものなり。
さにながら其の下す所、甚だ見分けの入るところなり。仲景三承気を立て、少し与へ多くあたえて将息す。傷寒論に熟すればことごとく知るなり。
小承気に曰う※2
「陽明病、潮熱し、大便微(すこ)しく鞕なる者は、大承氣湯を與うべし。鞕ならざる者は、之を與うべからず。若し大便せざること六、七日なれば、恐らくは燥屎(そうし)有り。之を知らんと欲するの法は、少しく小承氣湯を與え、湯腹中に入り、轉(てん)失氣する者は、此れ燥屎有るなり、乃(すなわ)ち之を攻むべし。
若し轉失氣せざる者は、此れ但(た)だ初頭(しょとう)鞕く、後必ず溏(とう)す、之を攻むべからず。之を攻むれば、必ず脹滿し食すること能わざるなり。水を飲まんと欲する者に、水を與えれば則ち噦(えつ)す。其の後發熱する者は、必ず大便復(ま)た鞕くして少なきなり、小承氣湯を以て之を和す。轉失氣せざる者は、慎んで攻むべからざるなり。」と。
是にて下すことは容易にせざることを知るべし。此の外、承気に戒たる言葉多し。
さて下すことの早過ぎたるは、熱をおびやかした許(ばかり)にて用に立たぬのみならず、却て熱さめかねる、或いは恊熱利に成るも有り。少し遅きはよし。即ち呉又可(ごゆうか)が胃中に集まるを待(まち)て下せと云は、此の所なり。
前にも言し如く、初めより大黄などの入りたる散藥を兼用することいわれ無し。其の度に至りたる所を下せば手に応ずることなり。傷寒論に反下と云う字は、皆誤下を云う。
表証未だ盡きざるうちは下すと、心下痞満或いは結胸などの事、皆反下と云う後に見えたり。能々心を留て読むべし。疫の初起は胃中には邪なし。然るに承気を用いて却って熱を加ゆるものなり。胃に伝るを待(まち)て下すべし。其の胃に伝たるを見分の事は追々にかたらん。亦、結糞に拘ることなかれの條と見合わすべし。
通鑑(『資治通鑑』)にも載す、耶律楚材(やりつそざい)と云し人は、蒙古の忠臣にて器量ものなり。「蒙古鉄木真(てむじん、チンギスハンの幼名)盡(ことごと)く夏城邑(ゆう)に克(か)つ。其の民鏨(たがね)で土石を穿ち、以て鋒鏑(ほうてき、ほこさきとやじりの意)を避く。免る者、百に一に無し。白骨野を蔽(おお)ふ。
蒙古の主、暑を六盤山に避(さ)く。月を踰(こ)え、夏の主、睍(けん 目が出たさま)か屈して降る。遂に縶(ちゅう しばる 捕らえるの意)して以て帰る。
夏の亡する時、諸将争て子女財幣を掠(かす)む。耶律楚材(やりつそざい)獨り書数部、大黄両駝を取る已(のみ)。軍士疫を病む。唯大黄を得て愈す可し。楚材之を用て萬人を活かす。(蒙古は後に元と国号す。)
補を恐る事は太陽にて解するは論なし。陽明の証になるもの多き故に、胃家実にて大黄の力を第一にする故なり。
又、李子建と云う人の傷寒十勧の文は大に規矩になること故、心得置くべし。聚方規矩にも出たるかと覚ゆ。
※1 傷寒論 94条
「太陽病未解。陰陽脉倶停。必振慓汗出而解。但陽脉微者先汗出而解。但陰脉微者下之而解。若欲下之宜調胃承気湯。又曰凡柴胡湯病証而下之、若柴胡証不罷者復与柴胡湯、必蒸々而振発熱汗出而解。」
※2 傷寒論 217条
「陽明病。潮熱大便微鞕者可与大承気湯。不鞕者不与之。若不大便六七日恐有燥屎乃可攻之。若転矢気者此但初頭鞕。後必溏。不可攻之。攻之必脹満不能食也。欲飲水者与水則噦。其後発熱者必大便復鞕而少也。以小承気湯和之。不転矢気者慎不可攻也。


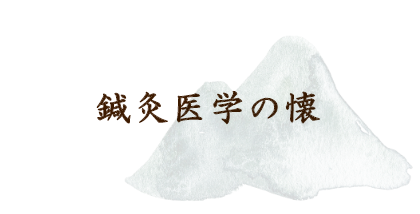



コメントを残す