金剛山にて
本篇は、現代病の病因・病理を把握する上で、重要な視点が記載されている。
近年急増している肺癌をはじめ、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、喘息、循環器疾患の一部などは、東洋医学的にはすべて肺臓の病変の範疇に属する。
これら疾患の病因にたいして、『 獨り肺のみにあらざるなり。』と述べられている点は、非常に重要な点であり、東洋医学の真骨頂と言える。
本篇に限らず素問では、病因の多くが外邪の侵入として述べられている。
素問の著わされた時代は、多くの人がまだ竪穴式住居など劣悪な生活環境であったことを想像すれば、当然であると考えられる。
翻って現代の生活状況を鑑みれば、これらの疾患を来す原因のほとんどは、たとえ単なる感冒であっても、内因に由来するものである。
直接、五臓を傷害するのは、『七情の過不足』であると、素問では記述されている。
これは、臨床的にも確かに、一致する。
現われている症状だけを、どれだけ追いかけても病が治らないのは、これらの疾患が増加している現状を見れば明白である。
対処療法しか、なしえない現代医療の状況において、東洋医学が本来内包している力を発揮する理(ことわり)が、明確に示されている。
これは、他の疾患においても同じである。
かつて『病や不幸は、外からやってくるもの』 から、『病や不幸は、内より迎えるもの』 と観念を切り替える必要がある。
原 文 意 訳
黄帝が申された。
肺を病むと、咳が出るようになるが、どのようなわけであろうか。
岐伯が申された。
五臓六腑に異常があれば、すべて咳が出るようになります。肺だけがひとり、病むことはないのであります。
帝が申された。
願わくば、その辺りのことを聞かせてもらいのだが。
岐伯が申された。
皮毛というのは、肺気の集まるところであります。その皮毛部位に、先ず邪気を受けますと、邪気は当然肺気に影響を与えることになります。
冷たい飲食物が胃に入りますと、肺経の流注に従って肺に上りますので、肺は寒します。
肺が寒しますと、内外の邪が皮毛に結集して気滞を起こしますので、肺気は宣散することもできず、下ることもできなくなって咳が出るようになるのであります。
五臓には、それぞれ病を受けやすい時期があり、邪を受けてしまえばそれぞれの臓の異変は伝変して、最終的に肺に影響を与えるのであります。
人と天地の気は、互いに交流しております。
従いまして、各五臓の気が盛んとなります時期に、軽微な寒邪を受けますと肺気の異常としての咳が出るようになりますが、甚だしいと下痢や痛みなどの他臓の症状が現れるのであります。
秋季に侵入する邪は、先ず肺がこれを受けます。
春季に侵入する邪は、先ず肝がこれを受けます。
夏季に侵入する邪は、先ず心がこれを受けます。
陰暦六月の至陰に侵入する邪は、先ず脾がこれを受けます。
冬季に侵入する邪は、先ず腎がこれを受けます。
帝が申された。
鑑別の要点はどうであるのか。
岐伯が申された。
肺咳の症状は、あえぎながら咳をしまして、呼吸音がいたします。激しいと唾液に血が混じります。
心咳の症状は、咳をすると胸の心の部位が痛み、喉の中に異物感があり、塞がったかのような感じがいたします。甚だしければ、咽喉が腫れます。
肝咳の症状は、咳をすると両脇の下が痛み、甚だしければ寝返りさえできず、強いて寝返りをすれば両脇の下が脹満します。
脾咳の症状は、咳をすると右脇の下が痛みます。その痛みは右脇の奥にあるようで、肩背にまで繋がって痛みます。甚だしいと動くこともできず、強いて動くと咳は劇しくなります。
腎咳の症状は、咳をすると腰と背が相い引き合うように痛みます。甚だしければ、咳と共によだれが出ます。
帝が申された。
六腑の咳はどうなのであろう。さらに、どこから病を受けるのであろうか。
岐伯が申された。
五臓の咳が長引くと、六腑に伝変するのであります。
脾咳が治らなければ、胃に伝変いたします。胃咳の症状は、咳をすると吐き気がし、吐き気が激しいと長い回虫が出てまいります。
肝咳が治らなければ、胆に伝変いたします。胆咳の症状は、咳をすると胆汁を吐きます。
肺咳が治らなければ、大腸に伝変します。大腸咳の症状は、咳をすると大便を失禁いたします。
心咳が治らなければ、小腸に伝変いたします。小腸咳の症状は、咳をすると放屁し、咳と同時に出ます。
腎咳が治らなければ、膀胱に伝変いたします。膀胱咳の症状は、咳をすると小便を失禁します。
久しく咳が続いて治らなければ、三焦に伝変いたします。三焦咳の症状は、咳をすると腹がいっぱいになり、食欲がなくなります。
これら五臓六腑が原因する咳は、結局のところ胃の気の状態に集約され、肺気がめぐることができなくなって咳を起こすのであります。
したがいまして、すべてに鼻水や唾が多く顔もむくむなどの症状が伴い、気が降りないので氣逆となり咳症状がでるのであります。
帝が申された。
これを治するには、どうすればよいのか。
岐伯が申された。
臓を治すには、五兪穴の兪穴を取り、治療いたします。
腑を治すには、合穴を取り、治療いたします。
浮腫には、その経絡から選んで取り、治療いたします。
帝が申された。よく理解できた。
原文と読み下し
黄帝問曰.肺之令人欬.何也.
岐伯對曰.五藏六府.皆令人欬.非獨肺也.
黄帝問うて曰く。肺の人をして欬せしむるは、何ぞや。
岐伯對して曰く。五藏六府、皆人をして欬せしむ。獨り肺のみにあらざるなり。
帝曰.願聞其状.
岐伯曰.
皮毛者.肺之合也.皮毛先受邪氣.邪氣以從其合也.
其寒飮食入胃.從肺脉上至於肺.則肺寒.肺寒則外内合邪.因而客之.則爲肺欬.
五藏各以其時受病.非其時.各傳以與之.
人與天地相參.故五藏各以治時感於寒.則受病.微則爲欬.甚者爲泄爲痛.
乘秋則肺先受邪.
乘春則肝先受之.
乘夏則心先受之.
乘至陰則脾先受之.
乘冬則腎先受之.
帝曰く。願わくば其の状を聞かん。
岐伯曰く。
皮毛なる者は、肺の合なり。皮毛先ず邪氣を受く。邪氣以て其の合に從うなり。
其れ寒の飮食胃に入り、肺脉從り上りて肺に至れば、則ち肺寒す。肺寒すれば則ち外内の邪合す。因りてこれに客すれば、則ち肺欬と爲す。
五藏各おの以て其の時を以て病を受く。其の時にあらざれば、各おの傳え以てこれを與う。
人と天地相參ず。故に五藏各おの治むる時を以て寒に感ずれば、則ち病を受く。微なれば則ち欬を爲す。甚だしき者は、泄を爲し、痛を爲す。
秋に乘ずれば則ち肺先ず邪を受く。
春に乘ずれば則ち肝先ずこれを受く。
夏に乘ずれば則ち心先ずこれを受く。
至陰に乘ずれば則ち脾先ずこれを受く。
冬に乘ずれば則ち腎先ずこれを受く。
帝曰.何以異之.
岐伯曰.
肺欬之状.欬而喘息有音.甚則唾血.
心欬之状.欬則心痛.喉中介介如梗状.甚則咽腫喉痺.
肝欬之状.欬則兩脇下痛.甚則不可以轉.轉則兩胠下滿.
脾欬之状.欬則右脇下痛.陰陰引肩背.甚則不可以動.動則欬劇.
腎欬之状.欬則腰背相引而痛.甚則欬涎.
帝曰く。何を以てこれを異にするや。
岐伯曰く。
肺欬の状、欬して喘息に音有り。甚しければ則ち唾血す。
心欬の状.欬すれば則ち心痛し、喉中介介として梗状の如し。甚しければ則ち咽腫し喉痺す。
肝欬の状.欬すれば則ち兩脇の下痛む。甚しければ則ち以て轉ずべからず。轉すれば則ち兩胠の下滿す。
脾欬の状.欬すれば則ち右脇の下痛み、陰陰として肩背に引く。甚しければ則ち以て動ずべからず。動ずれば則ち欬劇す。
腎欬の状.欬すれば則ち腰背相い引きて痛む。甚しければ則ち欬涎(がいぜん)す。
帝曰.六府之欬.奈何.安所受病.
岐伯曰.
五藏之久欬.乃移於六府.
脾欬不已.則胃受之.胃欬之状.欬而嘔.嘔甚則長蟲出.
肝欬不已.則膽受之.膽欬之状.欬嘔膽汁.
肺欬不已.則大腸受之.大腸欬状.欬而遺失.
心欬不已.則小腸受之.小腸欬状.欬而失氣.氣與欬倶失.
腎欬不已.則膀胱受之.膀胱欬状.欬而遺溺.
久欬不已.則三焦受之.三焦欬状.欬而腹滿.不欲食飮.
此皆聚於胃.關於肺.使人多涕唾.而面浮腫.氣逆也.
帝曰く。六府の欬は、いかん。安(いずく)の所に病を受けるや。
岐伯曰く。
五藏の久欬は、乃ち六府に移るなり。
脾欬已まざれば、則ち胃これを受く。.胃欬の状、欬して嘔す。嘔甚だしければ則ち長蟲出す。
肝欬已まざれば、則ち膽これを受く。.膽欬の状、欬して膽汁を嘔す。
肺欬已まざれば、則ち大腸これを受く。大腸欬の状、欬して遺失す。
心欬已まざれば、則ち小腸これを受く。小腸欬の状、欬して失氣し、氣と欬倶に失す。
腎欬已まざれば、則ち膀胱これを受く。膀胱欬の状、欬して遺溺す。
久欬已まざれば、則ち三焦これを受く。三焦欬の状、欬して腹滿し、飮食を欲せず。
此れ皆胃に聚り、肺に關(せき)し、人をして涕唾(ていだ)多くして面浮腫し、氣逆せしむるなり。
帝曰.治之奈何.
岐伯曰.
治藏者治其兪.
治府者治其合.
浮腫者治其經.
帝曰善.
帝曰く。これを治すること、いかん。
岐伯曰く。
藏を治する者は、其の兪を治す。
府を治する者は、其の合を治す。
浮腫なる者は、其の經を治す。
帝曰く、善し。


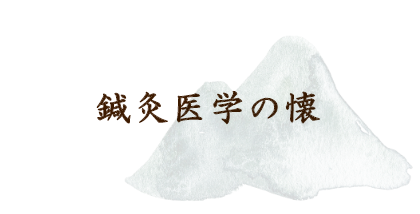




コメントを残す