病 因
病因とは、その病の起こる所の根本なり。其の本を治すれば他はひとりに良くなる。随分と念を入れて問うべし。即ち四診の問の字なり。病因と外証を合わせて方は処すべし。是れ素問に標本と称するものなり。
去りながら病因にかかわらず見証にて治すこともあり。是は時宜(じぎ)にしたがうにて、何病にもせよ急卒に倒れて手足厥冷すれば四逆湯なり。是外証にて方を付けねばならぬ病なり。
沈痾、痼癖に至りては、病因を極めて外証にて参(まじ)え考えれば、内因も符節の如くに合するものなり。かくなりたる時は死生を指すこと掌中にあり。又外証に主客の差別あり。是を主証、兼証とす。
さて病を問うに何の構(かまい)にならぬところ(まとはずれの意)を因にとると、方を付けて験もなし。
総て工(巧)拙は此に違いのある事なり。長病、痼疾ほど因をとらねば治すことならず。
たとえば先年下疳を 病たると云はば、病因となるの心なり。
婦人は第一に経行を問うべし。瘀血の因に属するもの、十に八、九なり。腰背疼痛、手足拘攣などは瘀血によるなり。
其の因のたずね様、疎末なれば奇験をとりがたし。
他日、人によりて病くせもあり。大そうになりさわぐ癖もあり。又一向に苦痛の事は物語らぬ人もあり。又医師の工拙(巧拙)を見ようとかくして見せる人もあり。
是は蘇東坡曰く。
疾有るに至りて療を求むは、必ず先に尽く告げるに患る所を以てす。而して後、診を求めば便(すなわ)ち医了然として患のこれ至る所を知るなり。
東坡の流、至極よし。さまでのことにもあらねども、病因隠れたるは、しれがたきことあり。
天明丁未(1787年)、元旦早朝する時、小吏医師を連れて馳せ行くを見る。
急病人やあると出仕して聞けば、富田総裁七十に近き人なりけるが、廟堂に於いて急病なるにより、同僚も三人有司の命にて行たりと云う。
やがて同僚も一同 帰り来 りて席につけば、一席の諸士何病にて如何なりと尋ね問うに、何か苦痛強く起き上がり起き上がりするを、ようやく脈を見たりと云う人もあり、中寒などにてあらんかと云う人もあり、中気の気味にもあらんか涎を流したりと云う人もあり、決定して病証を言い切りたる人なし。
余心に、拙き見様哉(かな)、何ぞ主証とさだまるものありそうなもの、と思いけれども、其の儘(まま)にて朝礼もすみて退出せり。
富田が嫡男、人を馳て曰く、かりに最(モ)寄りの由緒へ引き取たれば一診を乞うと。
云うにまかせ往きて診するに、なるほど先に見たる人々の名を付けかねたるも尤もにて、いかにも知りかねる。
朝衣のままにて巨燵(コタツ)へ臥して微にうなるばかりにて挨拶もなし。
脈は洪大にて数を帯び、頭より自汗出て手足逆冷す。中気のように見ゆれども、手足は痿たるとも見えず欠(厥)もせず。中寒と云いしも無理ならず。
腹を按ずるに満して痛むとみえて、中脘の辺へ指をつければ顔をしかめ眼中は常の通りなり。
先に営中にて服薬したるに吐逆して受けざるのみならず、時々嘔(吐)くことありと。
薬を飲むと皆吐逆したりと云うに因って前夜の様子を委しく問えば、出仕前に魚味にて酒を飲みたりと云う。其の魚に子もありしよし、沢山 食(しょくし) たりと云う。
さては宿食なり、酔後寒を受けたるばかりならずと中正湯を煎服す。何事もなく飲みたり。
二便あらば苦痛も退かんと思えども、衰老故(ゆえ)心元(こころもと)無く、哺時(日暮れ時)に又診すれば、小便通じて腹痛半を減ず。病人も少しは挨拶もある。
其の夜、大便通じて明日に至れば床に座す位になり、三、四貼にて全快したり。
是は因にばかり依りて治したり。
又疝気のある人は、其の疝の証候隠れて見えざることあり。
診法を精(くわ)しくして沈痾を治すこと度々なり。病因はおろそかにすべからず。
水腫、痢病、吐食、反胃、気癖などに疝の因なること有り。
南風がふくか雨にても催すと云う日より(天候)といえば、頭痛して上衝する人あり。桂枝の証か芎黄散の証か加味逍遥散かと云う病人は、其の因は虫積なり。
婦人にあれば、胡乱に血のみちとして治すれども、是は※芟(カリ)凶湯にて蚘虫を下せば再発せぬものなり。病因のことは万病に入用なり。
※芟凶湯(さんきょうとう)
紀藩の士、十三歳なりとぞ、安永甲午の年。京都にて通し矢を仕(し)たりるけるが、極めて秀たる事にてありき。
少し不快のことありて同盟藤岡氏なるもの療を乞うに、虫積の候ある故に芟(シン)凶湯を与えて其の病愈たり。
此の人、矢数をかけると左の肩、隱々と痛みたることありき。
蚘虫を下して後、肩の痛みを忘れたりとなり。虫積の害をなすこと思いもよらぬ事あり。芟凶湯を用いて知るべし。
然れども虫積を見分誤れば無益の薬なり。
眼病にも、痢病、瘧、水腫の類にも病因は虫積なるときあり、心を用いて診すべきなり。


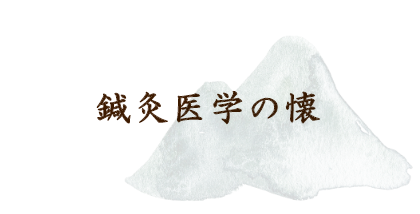

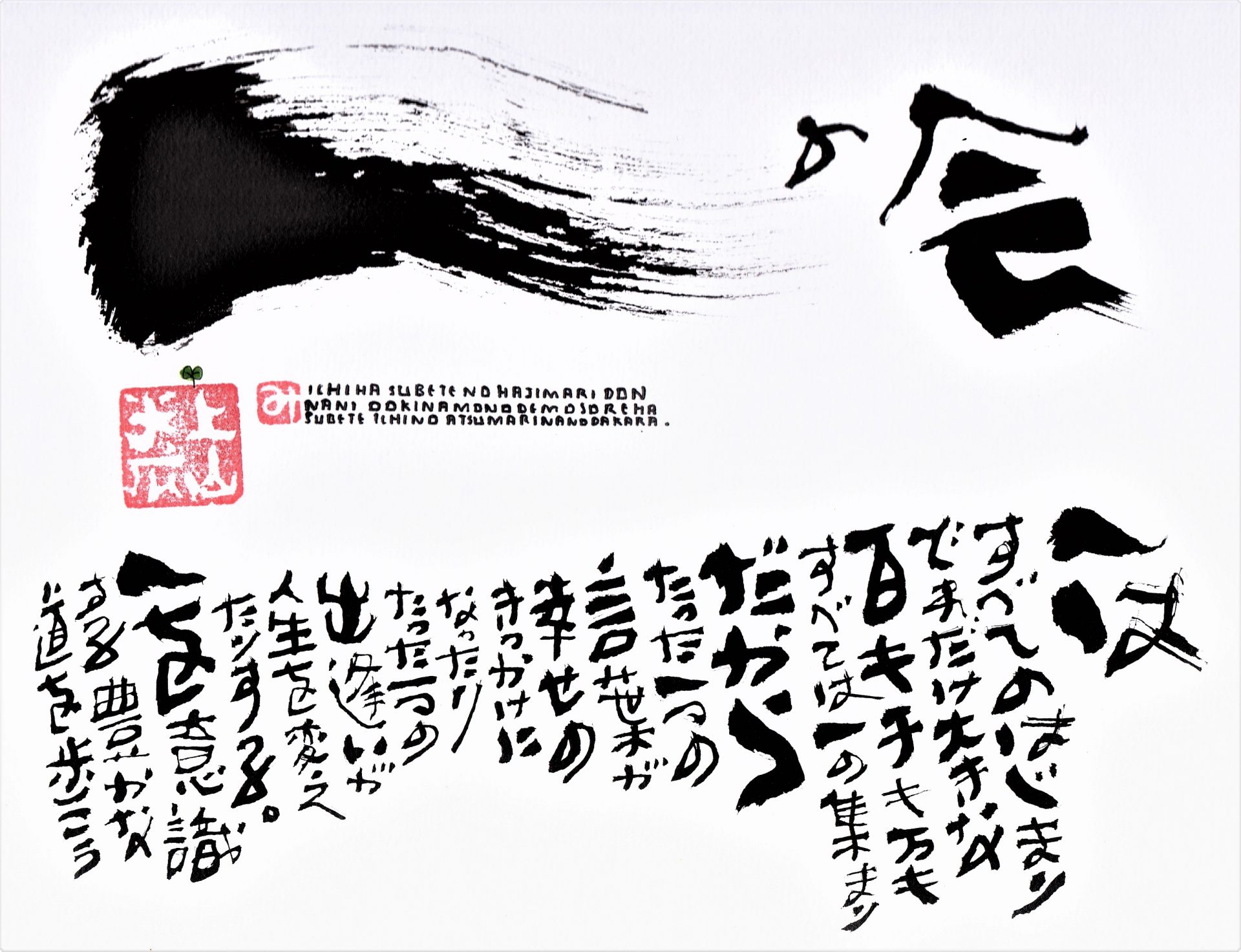

コメントを残す