カリンの花 於:泉北ハーベストの丘で
医聖、張仲景(150?~219)は、当時伝えられていた医学書を元に『傷寒雑病論』を著したとされているが、その序文の一説に素問、九巻(おそらく霊枢)の記述がある。
張仲景が、本篇≪熱論≫からヒントを得て、六経概念を構築したのだろうということは、容易に察することができる。
本篇の中で述べられている六経の内容は、臓象と経絡とを結びついているのに対して、張仲景の六経は、正邪抗争の場がどこであるのか。
つまり病位を意識しつつ、病の深さとバリエーションを、六つのカテゴリーに系統的・時系列的に整理したものである。
もちろん、経絡を意識したものであるとの異論もあるとは思うが、目を通して頂くとすぐに分かるとおり、傷寒論中では経絡の記述よりも、むしろ腹証の記載のバリエーションが圧倒的に多い。
しかも手足の寒熱の記載はあるにしても経絡を特定している箇所は、足の陽明に鍼をして伝変を防ぐなどのほんのわずかの記載しかされていない。
筆者が「傷寒論」を通読して感じることは、張仲景は経絡よりもむしろ、身体を空間として捉えていると考える。
それはともかく当時、張仲景が目にした素問と、現代に伝わる素問と同じかどうかは知る由もないが、時代を超えて概ね同じ内容のものを手にとって観ることができていることに、連綿とした数限りない歴代の医家に、自分自身も連なっているように感じて感慨深い。
本篇は、外感病について記述されたものであるが、最後に肉食について触れられている。
おおよそ発熱性疾患には、陽気の強い酒類や肉・油脂などはもとより禁忌である。
翻って現代で蔓延しているアトピーや膠原病などの自己免疫疾患や癌、橋本病やバセドウ氏病などの内分泌異常などは、何らかの熱が関与している場合がほとんどである。
戦後、日本人の食生活が大きく様変わりし、卵・肉や油脂などの陽気の強い食が日常的に食卓に上るようになり、情志の鬱積と相まって内熱を盛んにしている状態は、日常の臨床で度々目にすることである。
食文化の崩壊は、まことに憂うべきことである。
原 文 意 訳
黄帝が申された。
今日において熱病とされているものは、すべて悪寒がする傷寒の類であるとされているが、治るものと死する者がいる。
その死するものは、皆六、七日の間に死し、治るものは皆十日以上かかっているのは、どういう訳なのであろうか。その疑問を解く鍵が無い。願わくば、その点について聞かせてもらいたいのだが。
岐伯がこれに対して申された。
巨陽と申しますのは、諸陽がこれに属しております。この脉は風府に連なっております。従いまして、巨陽は諸陽を主っているのであります。
人が寒邪に傷られますと、発熱する病となりますが、高熱となりましても死ぬとは限りません。
ところが臓と腑が同時に寒邪に傷られますと、必ずといっていい程死を免れることが出来ないのであります。
帝が申された。
願わくばその症状を聞かせてもらいたい。
岐伯が申された。
傷寒に罹りまして、
一日目は、巨陽が寒邪を受けます。従いまして、巨陽の頭や項が痛み、背中全体から腰も強ばります。
二日目は、陽明に寒邪が侵入します。陽明は肉を主り、その脈は鼻を挟んで目を絡います。従いまして、身体は発熱し、目は疼いて鼻が乾き、身が悶えて安眠できません。
三日目は、少陽に寒邪が侵入いたします。少陽は胆を主ります、その脉は脇を循り耳を絡います。従いまして胸や脇が痛み、難聴となります。
これらのように、三陽の経絡すべてに寒邪を受けて病んだといたしましても、未だ臓に侵入していなければ、発汗させ寒邪を追い祓いますと、治るのであります。
四日目になりますと、太陰が寒邪を受けるようになります。太陰の脈は、胃中に広く行きわたって咽喉を絡っております。従いまして、腹満して咽喉が乾くようになります。
五日目には、寒邪が少陰に侵入いたします。少陰の脉は、腎を貫き肺を絡い、舌本に繋がっております。従いまして、口の中も舌も乾いてガサガサとなり、たくさん水を飲みたがります。
六日目には、寒邪が厥陰に侵入いたします。厥陰の脈は、陰器を行り肝を絡います。従いまして煩滿して陰嚢が縮み上がるようになるのであります。
これらのように、三陰三陽、五臓六腑すべて邪を受けて病んでしまいますと、栄衛は行らない上に五臓の気も通じなくなりますので、死すのであります。
もし、表裏ともに寒邪に侵されておりませんと、
七日目には、巨陽の病が衰えてきますので、頭痛も少しずつ癒えて参ります。
八日目には、陽明の病が衰えてきますので、身体の発熱も少しずつ癒えて参ります。
九日目には、少陽の病が衰えてまきますので、難聴であっても少しずつ聞こえるようになって参ります。
十日目には、太陰の病が衰えてきますので、腹満も減じて元のようになってまいりますので、無くなっていた食欲も回復いたします。
十一日目には、少陰の病が衰えてきますので、水を飲みたがる渇や腹満もなくなり、舌の乾きもなくなりますが、くしゃみをするようになります。
十二日目には、厥陰の病が衰えてきますので、縮み上っていた陰嚢もゆるみ、軽い下痢と共に堅く張っていた少腹も少しゆるみ、正邪ともにすべて去りますので、病は日を追って治まって参るのであります。
帝が申された。
これを治するには、どのようにいたすのか。
岐伯が申された。
これらを治すには、邪気を受けて塞がった、各々の藏脉を通じさせるのであります。邪気を祓い、藏脉が通じますと病は日を追って治まって参ります。
邪を受けましてから凡そ三日未満でありましたら、体表から祛邪いたしますので、発汗法を用いますと癒えて参ります。
満三日になりましたものは、邪が内向しておりますので、体内から祛邪いたしますので、下法を用いますと癒えるのであります。
帝が申された。
熱病が、もうすでに癒えたにもかかわらず、時としてすっきりと治りきらないのは、どのような訳なのであろうか。
岐伯が申された。
いまひとつすっきりいたしませんのは、熱が甚だしく食欲も無いのにも関わらず、無理に食事を摂ったためであります。
穀気と申しますものは、人の血の元であり陽気の源であります。このような状態になったものは、熱病は衰えたとは申せ、臓に余熱が遺っているものです。
そのような状態であるところに穀気が入ってまいりますと、余熱と穀気がせめぎあって合してしまいますので、今ひとつすっきりとしないのであります。
帝が申された。
なるほど、そうであったか。では、すっきり治すにはどうすればよいのか。
岐伯が申された。
その虚実を意識的に、はっきりと見定めた上でその従逆を調え、必ず治さなくてはなりません。
帝が申された。
熱を病んだ時には、何を禁ずれば良いのか。
岐伯が申された。
熱を病んでようやく少し治ってきたかなと思ったときに、陽気の強い肉を食しますと熱がぶり返し、多食いたしますと後々すっきりとせず症状が長引くのであります。
ですので、食欲が無いのに無理に食したり、肉を食すことを禁ずればよろしいのであります。
帝が申された。
その病が、陰陽・表裏の両経同時に寒邪に侵された場合、その經脉と病の症状との相関はどのようであるのか。
岐伯が申された。
両経同時に寒邪に侵された病は、
一日目は巨陽と少陰がともに病みまして、頭痛がし、口が乾いて煩滿いたします。
二日目は陽明と太陰がともに病みまして、腹が膨れまして身体が熱し、食欲が低下してうわごとやとりとめもないことを口走るようになります。
三日目は少陽と厥陰がともに病みまして、耳が聞こえなくなり、陰嚢が縮み上って意識障害を起こします。そうなりますと水分さえ入らず、誰が誰であるかとの人のみさかいもつかなくなり、六日で死するものであります。
五臓がすでに傷れてしまい、六腑も通じず栄衛の気も行らないという状態になり、三日もすれば死するというのは、どういう訳であろう。
岐伯が申された。
陽明と申しますは、十二経脉の長であります。
陽明の経は最も血気が盛んでありますので、人のみさかいが無くなって三日もすれば、陽明の経気が尽きてしまいますので、死するのであります。
凡そ、傷寒の病が温病へと変化いたしますのは、夏至の前でしたら温邪を病んだと判断し、夏至の後でしたら暑邪を病んだと判断いたしまして、暑邪は発汗させ、すべて出し切るまで止汗してはなりません。
原文と意訳
黄帝問曰.
今夫熱病者.皆傷寒之類也.
或愈或死.
其死皆以六七日之間.其愈皆以十日以上者.何也.
不知其解.願聞其故.
黄帝問うて曰く。
今夫れ熱病なる者は、皆傷寒の類なり。
或いは愈え或いは死す。
其の死するや皆六七日の間を以てし、其の愈ゆるは皆十日以上を以てする者は、何んなるや。
其の解を知らず。願わくば其の故を聞かん。
岐伯對曰.
巨陽者.諸陽之屬也.其脉連於風府.故爲諸陽主氣也.
人之傷於寒也.則爲病熱.熱雖甚不死.
其兩感於寒而病者.必不免於死.
岐伯對して曰く。
巨陽なる者は、諸陽これに屬すなり。其の脉は風府に連なる。故に諸陽の主氣と爲すなり。
人の寒に傷られれば則ち熱を病むと爲す。熱甚だしと雖ども死せず。
其の寒に兩感して病む者は、必ず死を免がれず。
帝曰.願聞其状.
岐伯曰.
傷寒
一日巨陽受之.故頭項痛腰脊強.
二日陽明受之.陽明主肉.其脉侠鼻絡於目.故身熱目疼而鼻乾.不得臥也.
三日少陽受之.少陽主膽.其脉循脇絡於耳.故胸脇痛而耳聾.三陽經絡.皆受其病.而未入於藏者.故可汗而已.
四日太陰受之.太陰脉.布胃中.絡於嗌.故腹滿而嗌乾.
五日少陰受之.少陰脉.貫腎絡於肺.繋舌本.故口燥舌乾而渇.
六日厥陰受之.厥陰脉.循陰器而絡於肝.故煩滿而嚢縮.三陰三陽.五藏六府.皆受病.榮衞不行.五藏不通.則死矣.
帝曰く。願わくば其の状を聞かん。
岐伯曰く。
傷寒、
一日巨陽これを受く。故に頭項痛みて腰脊強ばる。
二日陽明これを受く。陽明肉を主る。其の脉鼻を侠み目を絡う。故に身熱して目疼(うず)きて鼻乾く。臥するを得ざるなり。
三日少陽これを受く。少陽膽を主る。其の脉脇を循り耳を絡う。故に胸脇痛みて耳聾す。三陽經絡、皆其の病を受けるも未だ藏に入らざる者は、故(もと)より汗して已ゆべし。
四日太陰これを受く。太陰の脉、胃中に布き、嗌(えき)を絡う。故に腹滿して嗌乾く。
五日少陰これを受く。少陰の脉、腎を貫き肺を絡い、舌本に繋なる。故に口燥して舌乾きて渇す。
六日厥陰これを受く。厥陰の脉、陰器を循りて肝を絡う。故に煩滿して嚢縮む。三陰三陽、五藏六府、皆病を受れば榮衞行らず、五藏通ぜざれば則ち死するなり。
其不兩感於寒者.
七日巨陽病衰.頭痛少愈.
八日陽明病衰.身熱少愈.
九日少陽病衰.耳聾微聞.
十日太陰病衰.腹減如故.則思飮食.
十一日少陰病衰.渇止不滿.舌乾已而嚔.
十二日厥陰病衰.嚢縱.少腹微下.大氣皆去.病日已矣.
其の寒に兩感せざる者は、
七日巨陽の病衰え、頭痛は少しく愈ゆる。
八日陽明の病衰え、身の熱は少しく愈ゆる。
九日少陽の病衰え、耳聾は微(かす)かに聞く。
十日太陰の病衰え、腹減じて故(もと)の如くければ則ち、飮食を思う。
十一日少陰の病衰え、渇止みて滿せず、舌の乾き已えて嚔(てい)す。
十二日厥陰の病衰え、嚢縱(ゆる)み、少腹微かに下る。大氣は皆去り、病は日に已ゆ。
帝曰.治之奈何.
岐伯曰.
治之各通其藏脉.病日衰已矣.
其未滿三日者.可汗而已.
其滿三日者.可泄而已.
帝曰く。これを治するは、いかん。
岐伯曰く。
これを治するに、各おの其の藏脉を通ずれば、病は日に衰え已ゆ。
其の未だ三日に滿たざる者は、汗して已ゆべし。
其の三日に満る者は、泄っして已ゆべし。
帝曰.熱病已愈.時有所遺者.何也.
岐伯曰.
諸遺者.熱甚而強食之.故有所遺也.
若此者.皆病已衰.而熱有所藏.因其穀氣相薄.兩熱相合.故有所遺也.
帝曰く。熱病は已に愈え、時に遺(のこ)る所有る者は、何んぞや。
岐伯曰く。
諸々の遺れる者は、熱甚だしくして強いてこれを食う。故に遺り所有るなり。
此の若き者は、皆病は已に衰えて、熱の藏する所有り。其れ穀氣と相い薄(せま)りて、兩熱相い合するに因る。故に遺す所有るなり。
帝曰善.治遺奈何.
岐伯曰.視其虚實.調其逆從.可使必已矣.
帝曰.病熱當何禁之.
岐伯曰.病熱少愈.食肉則復.多食則遺.此其禁也.
帝曰く、善し。遺るを治すること、いかん。
岐伯曰く。其の虚實を視、其の逆從を調えれば、必ず已えざらしむるべし。
帝曰く。熱を病めば當(まさ)に、何をこれ禁んずるや。
岐伯曰く。熱を病みて少しく愈ゆるに、肉を食せば則ち復し、多食すれば則ち遺る。此れ其の禁なり。
帝曰.其病兩感於寒者.其脉應與其病形何如.
岐伯曰.
兩感於寒者.病
一日則巨陽與少陰倶病.則頭痛.口乾而煩滿.
二日則陽明與太陰倶病.則腹滿.身熱.不欲食.譫言.
三日則少陽與厥陰倶病.則耳聾.嚢縮而厥.水漿不入.不知人.六日死.
帝曰く。其の病、寒に兩感する者は、其の脉、其の病形と應ずること何んの如きか。
岐伯曰く。
寒に兩感する者は、病むこと
一日なれば則ち巨陽と少陰と倶に病む。則ち頭痛み、口乾きて煩滿す。
二日なれば則ち陽明と太陰と倶に病む。則ち腹滿し、身熱し、食を欲せず、譫言す。
三日なれば則ち少陽と厥陰と倶に病む。則ち耳聾し、嚢縮みて厥し、水漿入らず、人を知らず、六日にして死す。
帝曰.五藏已傷.六府不通.榮衞不行.如是之後.三日乃死.何也.
岐伯曰.
陽明者.十二經脉之長也.
其血氣盛.故不知人三日.其氣乃盡.故死矣.
凡病傷寒而成温者.
先夏至日者.爲病温.
後夏至日者.爲病暑.暑當與汗.皆出勿止.
帝曰く。五藏已に傷れ、六府通ぜず、榮衞行らず。是の如きの後、三日にして乃ち死すとは、何んぞや。
岐伯曰く。
陽明なる者は、十二經脉の長なり。
其の血氣は盛なり。故に人を知らざること三日にして、其の氣は乃ち盡く。故に死するなり。
凡そ傷寒を病みて温と成るものは、
夏至の日に先んずる者は、温を病むと爲す。
夏至の日に後る者は、暑を病むと爲す。暑は當に與に汗すべし。皆出して止むること勿れ。


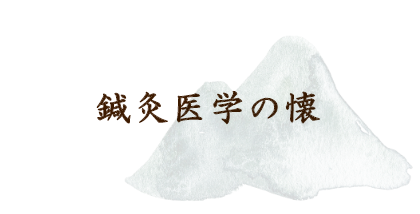



コメントを残す