因証数攻
下したる後、二三日か一二日、舌上復(ま)た胎刺を生ずるは邪の未だ盡きざるなり。
再び之を下して胎刺取れ切らずとも鋒芒(ほうぼう 刃物のきっさき、敵を攻撃する方向の意)とてさらさらすること無く、輭(なん やわらかいの意)になれども熱渇の止まぬは又下せ。
熱渇止み胎刺脱し、日後更に熱を生じ、又胎刺を生じたらば又下すがよし。
凡そ幾度下したと量計(ハカル)するはあしし。下(くだ)す証を見(アラワ)せば幾度も下すべし。
医の見透しあしきは疑いを生じて余り下し過ぎんとて、折角下しはたちても中途より止めることあり。
只、三四日もつづけて下すこともあり。又二日も下し、一日も休むことあり。其の休みの間は淡き薬にてよし。
前條の柴胡の類にて見合わせて置くべし。承気を多服する、少服するとは功者の入ることなり。若し過不及あれば誤ること多し。
○温疫論の治方を釈して案に備う。朱晦疇(しゅかいちゅう)と云うもの年四十五歳、疫を患いたりけるが、下す証ことごとく備りて手足ともに動くもならず、臥したる有様塑(さく ツチ人形)の如し。
目を閉じ口を張り、舌上胎刺かかり、其の苦しき所を尋ぬるに、答うることならず。
因て其の子に両三日前より用いたる薬は如何なる薬と問えば、承気湯の大黄を一両ばかり加えて三剤に及べども、効も見えぬ故仕方にあぐみ、只日を送れり。居ながら見るに忍びず。
願わくば一手段を付けて呉(クラ)れよと云うにより、脉を診するにまだ神あり。
是れ下す証そなわれども邪強くして薬のとどかぬなりと又大黄一両五銭煎服するに、目を時々動かす。
再び用ゆれば舌上ざらざらがとれたり。少しずつは物も言う。
三剤にして舌胎少し取れ目になりて神思もそろそろ爽(サワヤカ)になり、四日目に柴胡清燥湯を転方したれば、五日目には復た芒刺を生じ、煩熱の勢をなす。夫れによりて又前剤を用いて之を下す。
七日目に又承気養栄湯を用て熱少しく退く。八日目に大承気を用ゆ。手足少々ずつ動かすこともなる。凡そ半月の間に大黄を用ゆること、都(すべ)て二十両にして愈るに及ぶ。
又数日を経て始めて粥を用いて調理す。両月かかりて平復したり。
是は千人の内に三四人も有るか無きかと云う治療なり。夫れ故くわしく記して後案のためにすと云えり。
病愈結存
下後に脉も平になる時に、腹中に塊物ありて之を按ぜば疼(いた)む。其の身何となく腹内すきとせず、鬱陶しき様に覚ゆ。
時によりて又蛙の声の如くに、上の方、下の方にて鳴ることあり。此れ邪は已に盡(つき)たれども其の宿結尚除かざるなり。
之を攻めれば悪し。元気を破る。されども結のぶるあるものなれば補藥にてもなし。飲食も段々進める後は、胃気も復すると自然に愈るなり。嘗(かつ)て平復の後、半月ほど過て真黒の石の如き塊の下りたるを見たり。
下格
温疫愈後(いえてのち)何方(いずかた)もよけれども、二三十日大便不通してときどき嘔して、食すすまず、湯水も飲ても嘔吐することあり。
此を下格と云い、下が不通なる故上へ返すなり。翻胃(はんい)或いは寒気などと誤りて治すべからず。承気湯によろし。
たとえば涼風を求むるには南ばかり開ては風は入らず、北に窓を開けば風の入るに同じ。臭き大便下りたらば嘔吐は立ちどころに止むものなり。
さて吐が止った時、補藥を用ゆべからず。下焦閉ずれば直(ただち)に吐を発す。
前條の結存すると相似たれども、目利きの所は上下蛙声(あせい)と不嘔とを的とす。
気通ずると気塞がるの間に手段のつくことなり。
呉子の論、此の如くなれども承気は受けかねる故、柴胡加大黄或いは大柴胡にて治すべし。


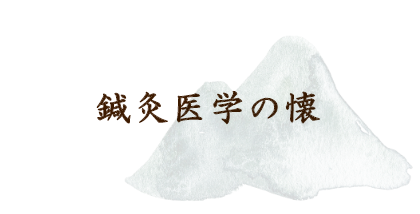
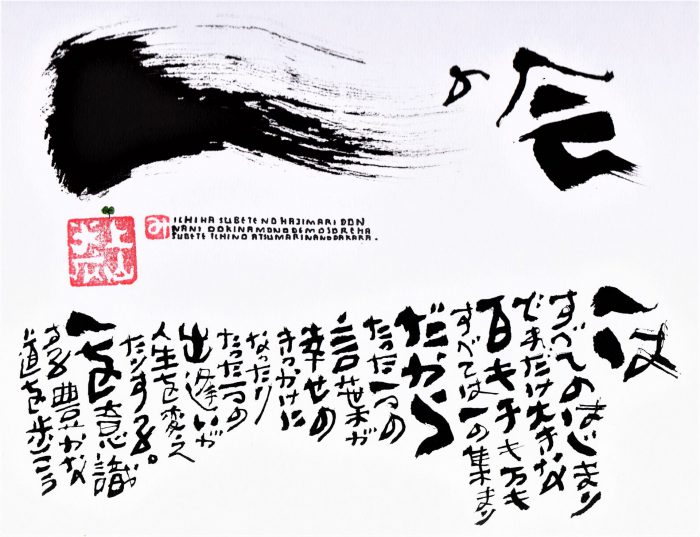




コメントを残す